水無(すいむ)神社例大祭
奇祭! 木曽のみこしまくり |
| 奇祭 |
7月22日、23日の2日間に渡って木曽町福島地区で
行われる(水無(すいむ)神社例大祭は、
赤松で造った400キロもの白木の神輿(○百万円)を、
縦に横にとまくる(転がす)天下の奇祭です。
|
| 由来 |
平安時代に戦乱が起き、飛騨国一宮の神社に火が放たれた
折り、木曽から出稼ぎに来ていた惣助(そうすけ)と幸助(こうすけ)というふたりの若者が火の中からご神体を持ち出し、神輿に納めて故郷の木曽へ向かったのだそうです。
ご神体が持ち去られたことを知った飛騨側の追ってが迫る中、ふたりは「そうすけ」 「こうすけ」と互いの名を呼び合い、神輿をまくって(転がして)峠を下り、現在水無(すいむ)神社が建てられている場所にご神体を持ち帰ったのだとか。
その由来に従い、神輿のかけ声は「そうすけ」「こうすけ」だけ。
「セイヤ」や「ワッショイ」のかけ声はこの祭りでは使いません。
そして、2日間の祭りの進行は
全てまくり(転がす)に向かって進んでいきます。
まくってまくって、深夜やっと神輿が壊れたと判定されると
ようやく祭りの終わり。
見物客は盛大な拍手で枠持ち(担ぎ手)を労い、同時に我が家の一年間の息災を祈ることができたことに感謝の念を捧げる
というわけです。
|
|
|
|
|
|
 |
| |
| 神事 |
厳粛な神事です。
観光用に大祭の日を土・日に変更することはありません。
女性が神輿を担ぐこともできません。ご神体が女性で、ヤキモチを妬かれるからだそうです。
役に着いた男性は精進潔斎をして祭りに臨みます。
赤ちゃんが神輿の下をくぐると丈夫な子になるとか、壊れた神輿のかけらを手に入れると息災だとか、いろいろな言い伝えも真剣に守られています。
そんな厳粛な神事ですが、子供用の小さい神輿や女性が乗る山車がちゃんと用意されています。子供が得意そうに綱を引いたり、おすましした浴衣姿の女の子が山車に乗るのもほほえましい光景です。 |
|
|
|
|
|
写真は神輿の飾りを取り払っているところ。
その後、飾りを取った白木の神輿を御岳の
見える場所まで運び、全員で遙拝。
まくりの準備に入ります。
木曽地方一帯は御岳信仰が強く
日々の生活でも、ことあるごとに
御岳を拝みます。 |
|
|
|
みこしのかけらを見物人に渡すところ。
一年を息災で暮らせると伝えられています。 |
まくり |
祭りのハイライトは道路を封鎖して行われる深夜の縦まくり。
400キロの神輿が地面にたたきつけられる音はすさまじく、樹木が倒れるような深く太い音が夜の谷間に響きます。
また、神輿が地面にたたきつけられる直前に枠持ち(担ぎ手)が神輿から飛び降りるという神技のような芸当には、安堵のため息と同時に拍手が鳴り止みません。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 以上 写真撮影 荒井 洋一 |
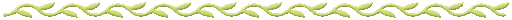 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
| |
春
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 草を食む春(開田高原) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 夏祭り |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S.Arai
|
![]()