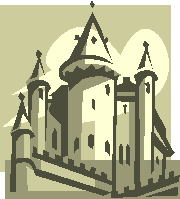
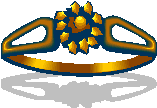
荒井 節子
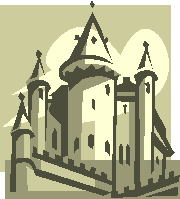 |
信州ゴールデンキャッスル(SGC) | 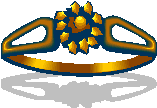 |
| 福寿草の里を訪ねて 荒井 節子 |
||
|
信州ゴールデンキャッスルは春は県下一の福寿草の群生地として、また秋には良質な松茸が採れることで知られた長野県、四賀村にあります。 四賀村の海抜は840m。前回のHPでご紹介した秘湯・青根温泉が海抜600mですから、いかに山深い場所に位置するかお解りいただけると思います。少し走れば北アルプスが望めるという美しい場所です。 この山深い村を目指して松本方面から車を走らせること数十分、村のふところ深く忽然と姿を現す白亜の建物を見上げる時、大抵の人は「エエッ!」と声を上げてしまうかもしれません。敷地3000坪、丘陵地を含めると2万坪、養老乃瀧創始者・木下様の個人コレクションをベースに昭和63年、美と健康(薬膳料理)をテーマにすべての展示品を販売する美術館としてオープンしたこの施設は、キャッスルという名に相応しいそれは立派な建物です。 |
 |
 |
案内を請い、長いアプローチを歩いてロビーに通されます。 ロビーにはりんどうの柄を織り込んだ柔らかなグリーンのカーペットが敷かれ、白い大理石のテーブルでは若いカップルが結婚式の相談をしています。 ここは世界の美術品を収蔵すると同時に神式、教会式の結婚式場も併せ持ち、近隣の人々に親しまれている場所でもあると伺いました。 |
「遠いところをようこそ」と案内に立ってくださるのはキャッスルの立ち上げ時に東京から移り住んで、以後こちらで働いているというお見掛けしたところまだ若い女性のスタッフです。 「東京からではお寂しくありませんでしたか」という質問に「社長さんも泊まり込んで一緒に働いてくださいましたから」と言うその物言いからも、お茶を運んでくださった別の女性の笑顔からも、素朴で穏やかな心遣いが感じられてこの会社の社員教育の良さが推察されます。「従業員が一番の経営資源」と考えて大切にするという養老の瀧の経営理念が、こうして実現されているということでしょうか。 昼時分でもあり、「まずはお食事を」とお弁当を戴くことになりました。 これはゴールデンキャッスル館内見学ツアーに出されるお弁当だということですが、因みにこの館内を見学できるのはデパートの外商の方、ここで結婚式を挙げられた方々、それにツアーを申し込まれた方と、3通りの方に分けられるそうです。 ツアーは4名様からで要予約、コーヒー・ケーキ付き1500円とお弁当付き3500円の2コースがあります。お弁当は美味しくボリュームもあり、お腹いっぱいになったところでいよいよ見学です。 |
 |
 |
まずは絨毯に敷き込まれたさくらの花が舞うロイヤルサロンのセーブル陶磁からです。 セーブル窯というのはパリ郊外セーブルに造られた窯の名ですが、王族達は18C〜19Cにかけ、威信をかけて数々の名品をこの窯で生み出しました。 その特徴はターキーズ・ブルーや桃色の地肌に金、赤、黄、などで彩色をした大変に華麗なものですが、しかし、発色具合は実際に焼き上げてみるまで解らないというのですから高価であるのも肯けます。この部屋には他にマイセン窯の陶磁、天蓋付きのベッドなどもあり、全体として宮廷美術が楽しめるようになっています。なかに、マイセンの陶版をいくつもはめ込んだキャビネットがありました。貴族の館に置かれていたものでしょうが、まさに特別な逸品という貫禄です(セーブル陶版入りのキャビネットも見事です)。 部屋を進むと神前結婚式場には、見たこともない豪華な打ち掛けも掛かっていました。 佐波理織というのだそうです。「金を織り込んであります」と説明されましたが、輝きはむしろプラチナに近い幻想的な織物で、鶴の恩返しの反物もかくやと思う美しさです。照明を落とす披露宴にはぴったりで「(少々値は張りますが)お貸ししてもいます」ということでした。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 部屋を進むと神前結婚式場には、見たこともない豪華な打ち掛けも掛かっていました。 佐波理織というのだそうです。「金を織り込んであります」と説明されましたが、輝きはむしろプラチナに近い幻想的な織物で、鶴の恩返しの反物もかくやと思う美しさです。照明を落とす披露宴にはぴったりで「(少々値は張りますが)お貸ししてもいます」ということでした。 名品揃いの館内ですが、部屋ごとに逸品中の逸品という美術品が置かれています。 例えば、珊瑚の間には天覧である土佐沖産の本ボケ珊瑚。本ボケという名前の由来は解りませんが、ぼけの花の柔らかいピンクに似た優しい色で大変心奪われる美しさです。 同様に天覧のものでは、銘石の間の菊花石がありました。菊花石自体が特別天然記念物ですが、天覧を賜った菊花石は特に菊の花が象眼のように浮き出ていてそれはそれは見事な石でした。 精巧な彫りの品々が置かれている象牙の間にも逸品がありました。 世界最大の象牙一対(ウガンダ産)と鷲の彫刻です。この鷲は明治天皇がニコライ2世の戴冠式に贈呈した折りに万一に備えて作られた予備の一体で歴史的にも貴重なものです。こうした美術品は、時の権力者が、ある思惑を持って作成させたものも多く時代背景を考えながら楽しむのも美術品鑑賞の楽しさです。 この象牙の間には根付けも多く、根付け愛好家でいらっしゃった故・高円宮様がご覧にいらっしゃったとも伺いました。 最後は屋久杉の間で古代の気を感じ(本当にそんな気持ちになります)、黄金の間で写真を撮っていただいて終わりです。 その間、1時間ほどでしょうか。美しいものを見るということは、心奪われ感動することですから結構疲れるものですが、案内に立ってくださった方は説明をしながら笑顔を絶やさず「ご満足いただけたでしょうか」と私達を気遣ってくださる余裕です。 見上げると壁に創業者・木下様(現在会長)のお写真が。その慈愛溢れたお顔を拝見しながら「会長さんはとても親孝行な方です」というお話も伺いました。 そういえば「養老の瀧」という社名も養老伝説から取ったそうですが、先ほど拝見した中国陶磁の部屋に、養老の滝の故事を描いた有田焼きの特注の壺が置かれていたことを思い出しました。親孝行という社是がこうして若い方を育ててもいらっしゃるのでしょう。四賀村は会長のご出身地であり、この建物は会長のご母堂のご実家跡に建てられたものと伺いました。 この美術館は、例えば着物や陶磁器のように人が人知をつくして美を追究した結果生み出されたものと、石や屋久杉のように人の力の及ばないものが並べて展示されています。美術館巡りが趣味の私ですが、どちらにしてもその圧倒的な美しさの前では自分が如何に平凡で未熟な人間かと思い知らされのが常のことです。そして、そんな平凡な人間が毎日健康で働けて、美しいものを見る機会を与えられたことを感謝する気になるのもいつもの通りでした。 |
 |
「お気をつけて」という言葉に送られて外に出ると福寿草の花が満開でした。 春にはまだ早い雪の中の福寿草に皆様のお気持ちを重ねて私は冷たくて美味しい空気を吸い込みました。 ご案内くださったスタッフの方々、また全てのお手配をしてくださった社長様に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。 |