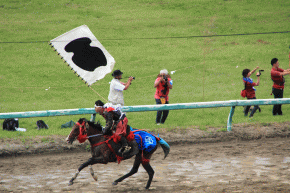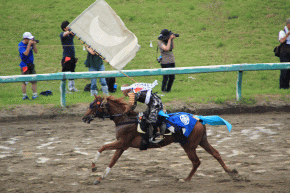|
(始めに) 思いたって「相馬野馬追ツァー」に参加しました。 震災直後は中止を余儀なくされるのでは、と危ぶまれた「相馬野馬追」ですが、あの大震災から8年が経ち、今年は、再び以前の規模で行われるのだそうです。 野馬追の知識があったわけではありません。相馬の地理や歴史もいまひとつでした。 「ちょうど日程が合ったから」という軽い気持ちだったのです。 でも祭場に向かうバスの中で「双葉町」「浪江町」という道路標識を目にし、また、遠く太平洋を望む山側の「こんな場所にまで?」という地点に津波到達の印を見つけたときには、「あの日この地に何が起きたのか」そして「そのことの重さ」が一瞬で理解できた気がしました。 (祭場にて) 祭場の「雲雀ヶ原」に到着。 遠くに山々が連なる一面の緑の原は美しく、赤や黄色で飾られた馬や武者達は凜々しい。まるで黒澤映画を見ているような壮大なシチュエーションに思わずテンションが上がり、カメラを構えること3時間半。炎天下でお弁当を食べることも忘れて、まさに魅せられたと表現したくなる「相馬野馬追」でした。 *お行列 相馬太田神社、相馬小高神社、相馬中村神社の各神社に供奉(ぐぶ)する各郷の騎馬隊が、先祖伝来の甲冑を身にまとい旗指し物を風になびかせながら、祭場となる雲雀ヶ原に向かって進軍する行事。 被害の大きかった双葉町・浪江町・大熊町は相馬小高神社に供奉している。 相馬家は鎌倉時代より幕末までお国替えのなかった希少な藩であり、総大将は今も 相馬家の子孫がつとめている。 尚、「相馬野馬追」は、相馬家の祖といわれる平将門が下総葛飾の牧で軍事訓練を行い、とらえた馬を神馬として氏神である妙見(妙見菩薩・北斗七星を神格化したもの)に奉納したことに始まると言われている。現在、国の重要無形民俗文化財。
*甲冑騎馬(かっちゅうきば)) 「相馬野馬追」ハイライトのひとつ。 正午、陣螺(じんがい)の音が鳴り響くと、武者たちは兜をぬぎ白鉢巻きをしめ、先祖伝来の旗指し物をなびかせながら風をきって疾走する。1周1000m、10頭立てで走る。 会場は満員で、立ち上がることはもちろん、移動することも容易ではない。 ただひたすら、目の前を駆け抜ける馬を300mmの望遠でのぞき込む。 以下、ISO・1000 1/1000秒のシャッターで撮影。
*神旗争奪戦 空中高く打ち上げられた花火の中から、赤・青・黄・白の御神旗がゆっくりと舞い下りる。 雲雀ヶ原一面に広がった数百騎の騎馬武者は、その御神旗を目指して掛け寄り、奪いあう。勇猛果敢な、まさに戦闘さながらの時代絵巻がくりひろげられる祭り最大のハイライト。 今年の最年少の出場者は、なんと6歳だった。
(見終わって) 今こうして写真を見返していると(繰り返し見ているというのに)、またまた深い感動が湧き上がってきます。たくさんの旅をし、その土地の美しさや人情には何度となく心ふるえたというのに、まったく不思議な経験です。 思うに、これは会場全体を覆っていた「郷土への愛」、そして「負けない!」という東北人のスピリットが、写真を通してこちらの心を揺さぶるからからに違いありません。 誰もが持っている自分の「ふるさと」や隠し持っている「負けじ魂」に向かって、射貫くようにまっすぐに、塊になってそれは飛び込んできたように思います。 お一人で参加された年配の男性が食い入るように「相馬野馬追」をご覧になっていました。 見終わって、ご家族に電話をされている声が聞こえてきます。 「体の方は大丈夫、うん、良かったよ。○○時に帰るから」 これから関東に帰る連絡のようです。名前もご事情も解りませんが、もしかしたら子どもの頃から「相馬野馬追」が身近にあった方なのかもしれません。 その誇らしそうなお顔を見ていたら、思わず「伝統あるお祭りっていいですね」と声をかけたくなりました。そして「ふるさとは、きっと復興しますね!」と。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||