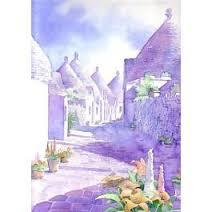世界遺産
アルベロベッロ (白川郷と姉妹都市です)
とんがり帽子の屋根が並ぶおとぎの国
|
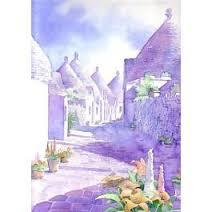 |
【 位置 】
長靴の形をしたイタリア半島のかかと(ブーリア州)にあります。オリーブで有名な農村地帯で、人口1万人ほどの小さな村です。
【 景観 】
土台も骨組みもないまま、この地方で採れる白い平たい石灰石を積み上げ、その上に円錐形の屋根を載せた可愛らしい家(トゥルリ)が約1000棟並んでいます。まるでおとぎの国に迷い込んだような景観です。屋根にはそれぞれに不思議な模様が描かれ、てっぺんには飾り石が置かれていますが、それが自分の家を識別するためか、はたまた魔除けのためかは不明だそうです。
【 歴史 】
「トゥルリ」の起源は15世紀にさかのぼります。日本のちょうど戦国時代でしょうか。
当時の領主が王様の許可なく町を興し、なかんずく税金を逃れるために農民たちにすぐに解体できる小さな家を造るように命じた結果、出来上がったのがこの家並だとか。
農民たちは部屋ごとに屋根を載せ、それをいくつも繋げて一軒として使ったそうですが、意外にもこの「トゥルリ」、強い日差しを遮り、雨水の有効利用に適した構造になっているんだとか。もちろん、今も住居として、あるいは土産店として現役で活躍中です。
強欲な領主に対抗して、農民たちは知恵を出し合い、したたかに生き抜いてきたことの証のような家並です。
|
|
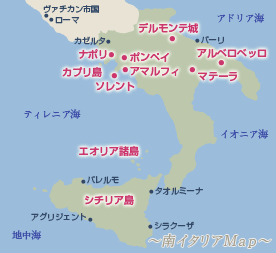
 イタリア発
イタリア発