|
昨年、「よりどころの言葉」と題し、私が、折に触れて思い出したり、何らかの行動をする場合の指針としている言葉について、雑文を掲載させていただいた。
その後、読んでいただいた方から、続きをとのお話があった。
本来、このようなことは、自分の中で思っていればよく、あまり人様に開陳するようなことではないので、気恥ずかしいのだが、書いてみることにする。
「東郷はかねて、『海戦というものは敵にあたえている被害がわからない。味方の被害ばかりわかるからいつも自分のほうが負けているような感じを受ける。敵は味方以上に辛がっているのだ』というかれの経験からきた教訓を兵員にいたるまで徹底させていたから、この戦闘中、兵員たちのたれもがこの言葉を思い出しては自分の気をひきたてていた。真之でさえこの戦闘中、東郷の言葉を思い出しては自分の気持を保った。
|
| 司馬遼太郎「坂の上の雲 八」(文春文庫 1999年) |
|
過日の掲載文に引き続く形になるが、司馬遼太郎の「坂の上の雲」からである。
日本海海戦が開始され、戦闘がたけなわになっていく際の描写である。
法的紛争では、当方の主張立証に対し、当然、相手方の反論反証がなされる。
それに対して当方が再反論し、相手方が再々反論するということが繰り返される。
事件の筋と証拠の強さで、既に見極めがついていれば、相手方の主張立証に対して過敏に反応する必要はないのだが、事実認定や法的評価がシビアで微妙という事件では、相手方の主張や提出される証拠に対し、逐一、神経を使わざるを得ない。
しかし、そのような場合に動揺しても得るものはなく、当初の基本方針(筋)を外さずに、相手方の主張と証拠に対し、冷静に評価を下して、適切に反論するしかない。
上記は、そうしたときによく思い出す文章である。
この文章は、引用されている東郷平八郎の言葉自体だけでなく、東郷が、かねてからこの言葉を末端の兵員まで徹底させていたということからも得るものがあるし、さらに、天才と言われた参謀の秋山真之ですら、東郷の言葉を思い出して自分の気持ちを保ったということからも、感ずるところがある。
「敵よりも大いなる兵力を集結して敵を圧倒撃滅するというのは、古今東西を通じ常勝将軍といわれる者が確立し実行してきた鉄則であった。日本の織田信長も、わかいころの桶狭間の奇襲の場合は例外とし、その後はすべて右の方法である。信長の凄味はそういうことであろう。かれはその生涯における最初のスタートを『寡をもって衆を制する』式の奇襲戦法で切ったくせに、その後一度も自分のその成功を自己模倣しなかったことである。桶狭間奇襲は、百に一つの成功例であるということを、たれよりも実施者の信長自身が知っていたところに、信長という男の偉大さがあった。」
|
| 司馬遼太郎「坂の上の雲 四」(文春文庫 1999年) |
|
同様に、「坂の上の雲」の一文である。
当方にとって筋的に非常に難しく、立証材料が乏しかった事件について、偶々、ある主張立証が功を奏し、逆転したということがあった。
その後、まさにそれを「自己模倣」し、失敗してしまったことがある。
「勝てる方法」など存在しないことを痛みとともに思い知った経験であった。
この文章は、その苦い経験と一体となって、私の中にある。
波騒は世の常である。
波にまかせて、泳ぎ上手に、雑魚は歌い雑魚は踊る。けれど、誰か知ろう、百尺下の水の心を。水のふかさを。
|
| 吉川英治「宮本武蔵 八」(吉川英治歴史時代文庫 1990年) |
|
吉川英治「宮本武蔵」の最後の一文である。
武蔵が、巌流佐々木小次郎を破った後、口さがない人々が、武蔵のことを様々に批判したということを受けての文章である。
このような「孤高」は、大事であると思う。
しかし、語弊をおそれずにいえば、これは自分のことだけですむ場面で通用することであって、仕事、特に、弁護士のように、「依頼者に分かってもらう」「裁判官に分かってもらう」「相手方に分からせる」ということが仕事の内容である者は、こういう「孤高の人」になってはいけないと思っている。
弁護士は、コミュニケーションをとるべく努力し続けるからこそ成立する仕事であり、コミュニケーションを放棄するわけにはいかない。
上記の文章をもって、このような読み方をするのは、その真意から外れるものであろうとは重々承知だが、あえて、感じたところを書かせていただいた。
以上、私の雑感にすぎない。お目汚しにならなければよいがと思っている。
| 終わり |
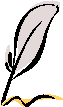
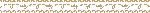 |
|