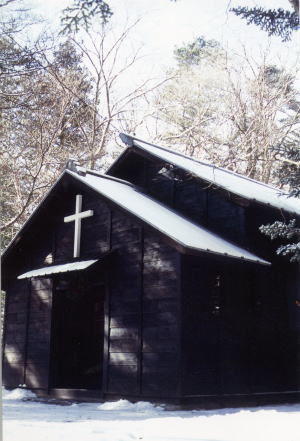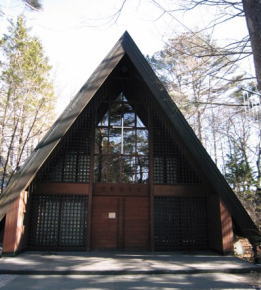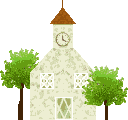|
 |
「軽井沢」と聞くと、たいていの方がうっとりと遠くを見るような目をし、それから「良いところですねえ」とおっしゃいます。「この間行ってきました」と言う方もいます。 そうです!みなさまに愛される「軽井沢」が今回のテーマ。この町の発展の様子を、歴史とともに巡っていきましょう。 あっ、「どうして歴史なのか」という質問ですか? だって、みなさまが憧れる「万平ホテル」の前身は旅籠「亀屋」だったってこと、知っていましたか?それに、今は寂れた追分宿跡に立って風に吹かれていると、堀辰雄を知らなくたって「風立ちぬ」という言葉が口から出てきますよ。 賑わう避暑地の奧にある、もうひとつの町の姿をお伝えしたくって、軽井沢の歴史を知りに「いざ、行き(生き)めやも」です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||