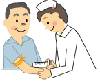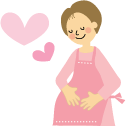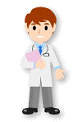 |
【 寄稿 】 骨髄バンクドナー登録 2mlの採血から Miki Ando |
 |
| 私は血液内科医として血液疾患の患者さんの診療を専門とし、現在は米国のある医科大で腫瘍に対する遺伝子治療の研究をしています。過日、現地(ヒューストン)日本商工会の情報誌に骨髄バンク登録についての話を掲載させていただきましたところ、その原稿を目にした貴事務所の所長から、「日本の方にも、もっと骨髄バンクについて知ってもらったらどうか」というお申し出をいただきました。折角の機会です。私の話を聞いてひとりでも理解者が増えたら嬉しいと、ここに原稿をお寄せすることにした次第です。 |
||
| 1 骨髄バンクとは | ||
骨髄バンクは、白血病などの血液疾患の治療として造血幹細胞移植(特に骨髄移植)が必要な患者さんのために、血縁者でない者から提供される骨髄液を患者さんに斡旋する業務を行う公的機関のことです。日本では、日本赤十字社及び各都道府県の保健所の協力を得て、骨髄移植推進財団が日本骨髄バンクの運営を行っています。 平成5年(1993年)に初の骨髄移植が行われました。 ところで、「骨髄バンク」登録を考えたことがある方はいらっしゃいますか? あるいはもう既に登録してくださっている方もいらっしゃるかもしれません。でも、実際に骨髄を患者さんに提供したことがある方はきっと少ないのではないかと思います。登録するかどうか迷った時、痛みはどの程度なのか、何回ぐらい病院に通い、何日ぐらい入院して仕事を休まないといけないのか、様々な疑問や不安が生じると思います。以下そんな疑問や不安にお答えしていきます。
|
||
| 2 ドナー登録 | ||
まず、ドナー登録ですが申し込み書類提出時に2mlの採血で完了します。この採血でHLA(ヒト白血球抗原)という白血球の型を調べます。HLAの組み合わせは数万通りあり、その適合具合でGVHD(移植後に起こる拒絶反応)の重症度が決まり移植の成功率に影響します。 兄弟間ではHLAが完全一致する確立は1/4ですが、兄弟で適合しなかった場合、HLAが適合する可能性は数百から数万分の一になります。たくさんのドナー登録が必要なのはそのためなのです! |
||
| 3 コーディネーター面談、採血 | ||
登録後HLAが適合するとドナー候補者として選ばれた通知が来ます。その後移植コーディネーターが日程調整をし、面談時に提供に関する詳しい説明を受けます。また、医師からも問診、説明を受けます。同意された場合は健康状態を確認する目的で採血を行います。
|
||
| 4 最終同意 | ||
この採血でドナーとなる健康基準を満たしていた場合、いよいよ最終同意となります。 最終同意の前までは提供意思の撤回ができますが、同意後は意思の撤回はできません。放射線や大量の抗がん剤を使い骨髄を破壊する前処置を始めた後に意思撤回され、予定通り造血幹細胞を輸注できないと本当に命にかかわるからです。 最終同意は移植コーディネーター、移植調整医師、弁護士立会いのもとドナー候補者とご家族の最終的な提供意思の確認、署名を行います。 |
||
| 5 精密検査 | ||
移植日の約一ヶ月前に採取病院で最終的な健康診査が行われます。 健常者であるドナーの方に万が一のことがあってはいけないので、呼吸機能検査、レントゲン、心電図、血液検査、尿検査などを行います。貧血、高脂血症、高血圧など手術の合併症の原因となる疾患の有無を検査し、コントロール可能な場合は内服薬での治療を行います。
|
||
| 6 入院 | ||
骨髄提供の場合:骨髄採取日の前日に入院し、全身麻酔下で腸骨に針を刺して骨髄液採取を行います。一回の採取で12〜20ml/kgの骨髄液を採取します。その際、循環血漿量低下に伴う血圧低下や貧血などを起こす可能性があるため、あらかじめ鉄剤を投与したり、数回自己血を採取し保存しておき骨髄採取時に返血します。採取された骨髄液は、骨組織などが混ざるのでメッシュを通しバッグに詰め、待機していた移植施設の担当医師が受け取り、当日患者さんに点滴で投与されます。手術中は全身麻酔のためほとんど痛みを感じないと思いますが、手術後は鈍痛や傷の痛みを感じます。鎮痛剤、座薬で対応し、大体の方が数日で日常生活に戻り、平均一週間以内で痛みが消失します。入院期間は4日間が一般的です。 末梢血幹細胞提供の場合:骨髄バンクでは平成22年10月より末梢血幹細胞移植を導入しています。これにより、ドナーの方と患者さんのご意向を踏まえて、骨髄移植と末梢血幹細胞移植のいずれかを選択できるようになりました。末梢血幹細胞移植の場合、採取日の3〜4日前にG-CSFという白血球を増やす薬を注射します。末梢血中に造血幹細胞を動員し、流れ出た細胞を連続血液成分分離装置を用いて体外循環(アフェレーシス)を行いながら採取します。通常一泊二日の入院で採取します。 検査や入院の費用は一切かかりませんが、休業補償は残念ながら出ません。しかし最近は「ドナー特別休暇制度」を導入している会社も増えてきました。
|
||
最後にさい帯血バンクについても触れておきたいと思います。 臍帯血とは母親と胎児を結ぶ臍帯と、胎盤の中に含まれる血液のことです。臍帯は出産後は不要となりますが、その血液中には骨髄と同様の、血液細胞を作り出すもとである「造血幹細胞」がたくさん含まれています。臍帯血は従来分娩時に廃棄されていた臍帯の中の血液を採取するため、採取時のドナーへの負担というものが存在しません。通常、胎盤娩出後早期に臍帯静脈に針を刺して採取します。細胞数が限られているため、生着遅延や生着不全がおきる可能性も高くなりますが、骨髄移植に比べてGVHDは重症化しにくいといわれています。驚くほど小さくパックされた臍帯血が白血病などの病気の方の命を救うことができるのです。
みなさまの善意で支えられている造血幹細胞移植です。ドナーとなってくださる方の暖かい気持ちを真摯に受け、移植を行う医療チームのメンバーもまた一生懸命働いています。楽な仕事ではありませんが、いただいた幹細胞が生着したときはひと安心、移植後GVHDや感染症を乗り越え無事退院したときは心から嬉しく感じます。 大まかな説明ですが、骨髄バンクやさい帯血バンクのドナーになろうかなと考えている方の助けになり、少しでも裾野が広がれば幸いです。骨髄提供は決して簡単なことではありませんが、移植治療を必要とする多くの方々が適合するドナーを今も待っているのです。 |