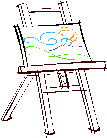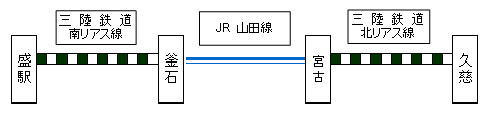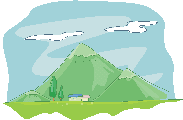 |
�� �� �� �� ��
|
 |
�@�@ �@�@
�@�m�g�j�@���̘A���e���r�����u���Ђ����v�̕����K�˂Ă݂܂��H �@���{�ŋ�����H�ׂāA���ܖ�Ŕ��p�فA���łɑ���L���Ĕ��n�̐�i���ʐ^�Ɏ��߂�E�E�E����ȗ��̃v�����͂������ł��傤���B �@�N�₩�ȑo�̓��c�_�A���������\�̐ڕ��n���A�����āA�����N�Ԃ̔n���ω��B��l�����̊肢��w�����ė����s�����Ă����R�̘[�̐_�l�́A�������₩�ȕ\��ł��Ȃ���҂��Ă��܂��B�����A���ꏏ�ɂł����܂��傤�B �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@+++++++++++++++++++++++++++ �@�@  �@�@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||