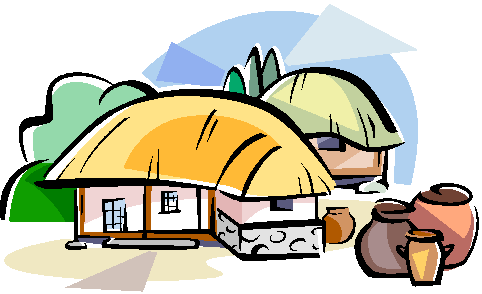 |
秘境への旅そしてお土産 Arai Setsuko |
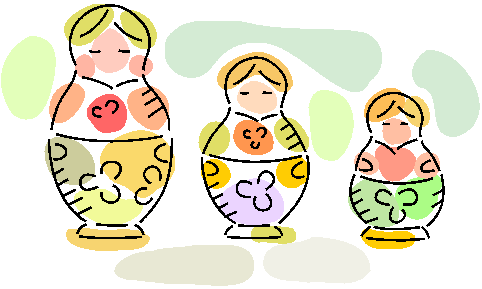 |
| 幼い頃に仰ぎ見た、山の彼方への憧れ今も忘れ難く、時間(お金)ができると出掛けてしまいます。 昔ほどではないにしても、アクセスの悪さは今も変わらず、夕闇迫る頃、ようやく宿にたどり着き、ほっとして宿の温泉に浸かる時、外はすでに漆黒の闇。 「隠れ里」などと呼ばれる秘境の姿は、こういう闇の中にこそ、現れる気がします。 見上げると、きらめく満天の星々も、思い出すと出掛けたくなる、秘境の魅力のひとつです。 |
 |
 |
| (福島県・舘岩村・前沢集落) 会津四家と称された只見川沿川の山内氏が伊達政宗に滅ぼされた後、家臣が移り住んだと伝えられています。豪雪地帯のために、母屋に曲家が付けられ、そこで馬が飼われました。 集落全体が統一された景観を保っているため非常に美しく、いつまで見ていても飽きません。 舘岩村には他に、水引集落と呼ばれる集落がありますが、こちらはもう少し素朴です。 この日は、近くの木賊(とくさ)温泉に泊まりました。熊鍋を食べ、さて温泉に入ろうと立ち上がったら、案内してくれた知人が「熊よけに」と真面目な顔で、バッドを取りだしたのでこちらも本気で驚きました。 |
|
 |
 |
| (富山県・五箇山・相倉集落) 幹線道路から道を逸れ、巾着型に広がる集落に入ると、そこは「日本昔話」の世界です。白川郷ほどには観光客もなく、その分、趣も深く、感動も大きい! 五箇山が平家の落人部落だと言い伝えられているのは有名です。倶利伽羅峠で木曽義仲と戦った平惟盛の残党が逃げ隠れたと伝えられています。 一方、南北朝時代に吉野朝の遺臣によってこの地域が開拓されたとも伝えられ、現在の住民はこの末裔だという人もいます。五箇山に入った仏教は吉野朝皇子の宗良(むねなが)親王によって 伝わったとも言われています。いずれにしても、ここは「隠れ里」であったということでしょう。 この夜は、集落の中の一軒に泊まりました。囲炉裏を囲んで、イワナを食べながら「クギを1本も使ってない」とか「囲炉裏の煙で燻されて虫がいない」とか「世界遺産の登録には住民が随分話し合った」などと、合掌集落について飽かずに話を聞いたことが、思い出されます。 右の写真は富山県、彫刻で有名な井波市で購入したもの。可愛いお地蔵さんが気に入っています。招き猫は商売繁盛のために購入? |
|
 |
 |
| (長野県・栄村・秋山郷・切明) こちらも平家の落人が隠れ住んだと伝えられています。 信越国境にまたがる秋山郷は、平家が隠れ住んだと伝えられ、かっては「またぎ」以外に殆ど人が入らなかった、という豪雪地帯です。 昭和2年にようやく戸籍ができ、昭和11年までは義務教育が免除された地域さえあったというのも驚きですが、長いこと社会と隔絶されていたために、中津川(写真にある川)に沿って点在するいくつかの集落には、つい、最近まで、集落独自の奇習?風習が、あったそうです。 そんな秋山郷も、林道ができて今では様変わりです。 年間を通して車が入るようになり、苗場山登山や渓流釣りを楽しむ人の他、新緑、紅葉と四季折々を楽しむ人が増え、シーズン時は観光客で賑わうようになりました。 この写真は、「切明」と呼ばれる、最奧の集落で撮ったものです。この地に湧く、切明温泉は、宿で借りたスコップで河原を掘って入る、野趣溢れるものですが、他にも赤湯(鉄分)が湧く温泉があり、こちらもまた、いかにも効用がありそうです。 右の写真は、木地師の家で購入したお椀です。 桜と栃を使っています。 |
|
 |
 |
| (長野県・木曽・御嶽山) 今ではどうか解りませんが、かって木曽福島という町は御嶽登山へのベース・キャンプでした。 夏になると、白装束に身を包み、金剛杖を持った「御嶽教」の信者さんが、講を組んで朝早く御嶽登山に出掛ける姿をたくさん見かけたものでした。 大人になってからですが、ある夏の未明、山際が明るくなったかと思うと、一条の光が御嶽山の頂上に差込み、そのうちの一つが、まるで灯明の明かりのように、真っ赤に燃え上がるシーンを目にしました。あまりの神秘さ、荘厳さに、子供の頃、少々怖い思いで眺めていた、御嶽教の信者さんの気持ちがいっぺんに理解できた気がしたものでした。 カメラを構えたら、もう、色が移ろってしまったのが、素人故の油断。今でも残念でなりません。 この山の頂上付近で雷鳥を見たのも、思い出です。 木曽谷は、いうまでもなく、木曽義仲、縁の地。 義仲に関する史跡が数々ありました。挙兵前に禊ぎをしたと伝えられる滝は、町民のハイキングコースでしたし、毛髪を埋めたと伝えられる墓は、こどもたちの「かくれんぼ」によく使われました。友人には義仲の四天王(家臣)の末裔もいたりして、思えば木曽谷は、不思議な魅力を持った山峡(やまかい)でした。 右の写真は森林浴発祥の地、赤沢美林で購入したひのきのコップ。非常に使い勝手が良く重宝しています。 |
|
 |
 |
| (長野県・大鹿村・大池高原) 標高1500mの大池高原で出会ったのは、まさに「天上の青」(これは曽野綾子さんの小説のタイトルですが)、ヒマラヤ4000mの高地に咲くという、幻の、青いケシの花でした。 本当に美しかった! 農園主さんは、最初は出荷しようと(儲けようと?)このケシの栽培を始めたそうです。 しかし、平地に降ろすと、一晩でしおれてしまうということで、今は、観光農園として、山道を登ってきた人だけに、この花を見せています。 「やはり野に置けスミレ草」 入場料500円也。 大池高原がある大鹿村は、五箇山に仏教を伝えたという宗良(むねなが)親王が、吉野朝再興を願って隠れ住んだと、言われています。 また、この村の鹿塩地区は、不思議なことが多く、例えば、海水のような塩辛い温泉が湧き出す、猫にノミがいない(これはTV局が実験済み)、蕨に灰汁がない、等々ですが、何故なのか、その理由が解っていないところが、さらにミステリアスです。 右の写真は、宿で購入した塩。 温泉の隣で、製造しています。 |
|
 |
 |
| (長野県・長谷村・分杭峠) 分杭(ぶんぐい)峠はゼロ磁場地点です。近頃はパワー・スポットとして有名になり、休日ともなると何故か若い人で賑わっています。 ゼロ磁場とは、地殻変動のエネルギーがぶつかりあって、N極とS極の磁気が互いに打ち消しあう場所だそうです(誰か持っていた磁石の針がくるくると回っていました)。 こういう場所は、マイナスイオンが発生しやすいそうですが、確かに、体の中を空気が流れていくような、大変気持ちの良い感覚がありました。 ところで、長谷村は南アルプスの登山口です。 南アルプスの北沢峠に登ると、南アルプスの開発に尽くした、竹沢長衛(ながえ)の小屋があり、「娘さんよく聞けよ」と歌われた「山男の歌」は、大正時代に、学生がこの小屋で歌って全国に広まったと、伝えられています。 こういう場所に立って、山を眺め、山男のロマンに触れて少し感傷に浸ってみると、いつも、目先のことに追われてばかりの自分が、別の自分になっていることに気がつきます。 パワー・スポットとは「そんな気分転換の手伝いをしてくれる場所」のように、私には思えました。 この日一日、私は正しく、ストレス・フリーであったと思います。 右の写真は、ゼロ磁場地点で購入した天然水です。くせがなくて、美味しい! |
|
旅の途中で出会う、一瞬の美しい風景も忘れがたいものです。 九十九折りの山道を曲がった途端、虹のように空に出ていた北アルプスの山並み、山奥の集落で、村人に寄り添うように咲いていた、樹齢1200年の神代桜、そして、森の中に広がっていた2輪草や山の棚田に舞うホタル。 今でも鮮やかに思い出す、こうした美しい風景に出会うたび、私は「この村の人たちは、この景色があるから、厳しい冬を乗り越えられるのだな」と、感じて、その地を愛している村の人たちを一層、好きになるのでした。 カメラを手にして10年近く。いつの間にか、写真を撮るときには「ありがとう」と、心の中で頭を下げるようになりました。それから、なるべく村の人の話を聞くことや、村の歴史を知ろうと、心掛けることなども。自然から学んだことは大きかったと思います。 ところで、唐突に出ている下の写真、いったい何だと、お思いでしょうか。 おもちゃのように見えますが、実はこれは、何とか言う貝が抱いていた、天然の真珠のネックレスです。秘境というより、仙境という方が近い、奄美の岬で、養殖真珠の業者さんから譲っていただきました。養殖ものなら2倍は大きいものが買えたとは思いますが、貝が自力で創った世界でたったひとつのもの、大変気にいっています。山のお土産ばかりの私のコレクション(というほど高価なものはない!)のなかで数少ない、海で手に入れた宝物です。 |
 |