 |
「扶氏医戒之略」と弁護士 弁護士 舘 彰男 |
 |
| 常々、弁護士と医師は似ているなと感じている。 どちらも、「悩みを抱えた方から相談を受け、問題点を確認し、専門家としての知識と経験から、最善の解決策を導くことが要求される」というプロフェッショナルである。 医師は、病気や怪我をした方が診療を受けに来られると、問診し、病気や怪我の原因を検査・診断し、高度の医学知識と経験に基づき、どのような治療方法が良いかを考え、最善の治療を施して、患者の回復を目指す。 弁護士は、法律問題を抱えた方が相談に訪れると、ご相談内容をお聞きし、証拠をもとに法的問題を確認・判断し、高度の法律知識と経験に基づき、どのような解決方法が良いかを考え、最善の方法と思われるやり方をもって、問題の解決を目指す。 いずれもサービス(医療サービス、法的サービス)を提供するプロである。 プロであるから、仕事は100%できて当たり前であり、ミスが許されない。医師にミスがあった場合、人の生死にかかわる。弁護士にミスがあった場合、人の人生を左右する。 「ヒポクラテスの誓い」と並び、医業の世界では有名であるが、「扶氏医戒之略」(ふし いかいのりゃく)という、緒方洪庵(1810〜1863)の書いた、医師としての戒め(「医戒」)がある。 「扶氏医戒之略」は、もともとは、ドイツの医師フーフェランド(「扶氏」。Chrstoph Wilhelm Hufeland (1762―1836))が著した「医学必携」(Enchiridion Medicum(1836))の巻末に付されていた戒めを、緒方洪庵が抄訳したものであって、全部で12箇条ある。 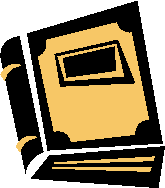 この「扶氏医戒之略」(文末に引用)について、試みに、「医(医師)」を「弁護士」に、「病者」を「相談者(又は依頼者)」に置き換えて、弁護士への戒めとして読んでみると、不思議なほど違和感がない。 この「扶氏医戒之略」(文末に引用)について、試みに、「医(医師)」を「弁護士」に、「病者」を「相談者(又は依頼者)」に置き換えて、弁護士への戒めとして読んでみると、不思議なほど違和感がない。例えば、「(4)学術を研精するの外、尚言行に意を用いて病者に信任せられんことを求むべし。」は、弁護士ならば、法的知識の研鑽を常に行い、正確な知識をもって、依頼者に対し、リーガルリスクの説明を分かりやすく十二分に行い、信頼関係を構築することが大切であるという文意で理解できる。この文言に続く「然りといへども、時様の服飾を用ひ、詭誕の奇説を唱へて、聞達を求むるは大に恥るところなり。」という「戒」も、単独説を振り回しても役にたたず、通説判例を踏まえた、裁判所に通用する説得力のある法的議論が必要であるという趣旨で受け取れる。 「(7)不治の病者も仍其患苦を寛解し、其生命を保全せんことを求むるは、医の職務なり。棄てて省みざるは人道に反す。」は、弁護士ならば、法的に勝訴は困難と思われたとしても、「勝てません」ではなく、リスク説明のうえ、和解などにより何らかの形で依頼者の保護が図れないかを模索するべきであると読むことができる。 「(10)同業の人に対しては之を敬し、之を愛すべし。たとひしかること能はざるも、勉めて忍ばんことを要すべし。決して他医を議することなかれ。人の短をいうは、聖賢の堅く戒むる所なり。彼が過を挙ぐるは、小人の凶徳なり。人は唯一朝の過を議せられて、おのれ生涯の徳を損す。其徳失如何ぞや。各医自家の流有て、又自得の法あり。漫に之を論ずべからず。老医は敬重すべし。少輩は親愛すべし。人もし前医の得失を問ふことあらば、勉めて之を得に帰すべく、其治法の当否は現病を認めざるに辞すべし。」も、セカンドオピニオンを求められたときの弁護士がとるべき姿勢として考えることができる(但し、(12)後段の「実に其誤治なることを知て、之を外視するは亦医の任にあらず。殊に危険の病に在ては遅疑することあることなかれ。」という視点も大事だろう)。 ほかの条も同様であり、弁護士のとるべき姿勢や考え方として読んでみたとき、いずれも頷くことが多い。 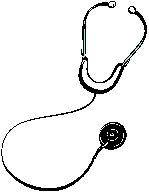 また、相談者から受ける質問に対し、医師を例にして説明すると、納得していただけることもある。 また、相談者から受ける質問に対し、医師を例にして説明すると、納得していただけることもある。例えば、「この訴訟は勝てますか。」とか、「勝つ確率は何パーセントですか。」という質問がある。 弁護士倫理について定めている弁護士職務基本規程は、依頼者に有利な結果となることを請け負うことを禁止しているから(同規程29条2項)、勝訴がほぼ確実と思われたとしても「勝てる」と断言することはできないし、むしろ、どんなことが起きるか分からない以上、可能性が低いリスクでも説明する、ということが実務的には無難と思われる。 しかし、依頼者が、自分の不安を和らげるため「勝てると言って欲しい」等と言うこともあって、回答を工夫することが求められる。 回答方法は各弁護士によっていろいろあると思うが、例えば、「医者は、どのような手術のときにも、100%成功すると約束したりしないで、『全力を尽くします』と言うでしょう。弁護士もそれと同じです。この事件の証拠関係からすると勝訴可能性はかなりあると思いますが、〜の点に対する反証があり得るので、予断を許さないと思います。いずれにしても全力を尽くします。」と説明すると、納得していただけることがある。 そのほかにも、例えば、「たくさん事件を抱えているようですけど,取り違えたりしないのですか。」という質問には「医師は、たくさんの患者を抱えていても、病状は一人一人違い、それぞれの方の個性もあるので、取り違えないでしょう。弁護士の抱える事件もそれと同じです。」と回答したり、「こんな相談を持ち込んですみません。」と言って、相談したこと自体を恥ずべきことと思っている方には「事件は病気みたいなものです。病気にかかったこと自体は仕方ないことで、何も恥ずかしいことはないです。病気を治す=事件を解決することに専念しましょう。」と話したりもする。 逆に、証拠収集に尽力しない依頼者には、「病気は、患者が治ろうとする気持ちを持って頑張らないと治らないと言われるでしょう。事件も同じで、ご自分で頑張ろうとしないと、弁護士だけがやろうとしても駄目です。」と話すこともある。 当事務所が、多くの医療機関の顧問をさせていただいているという関係から、医師と接する機会も多いので、このような印象が生ずるのかもしれない。 ただ、根本的に、弁護士と医師は、悩みを抱えた人を癒すことを業とするプロフェッショナルであって、基本的な理念が共通しているからであると理解している。 自分自身が、「医戒」に恥じない業務遂行をしているかというと、日々、自省の念を禁じ得ないところである。 以上、雑感である。日々思っていたことについて、今回、機会をいただいたので、連ねてみた。読了に耐えれば幸いである。
|