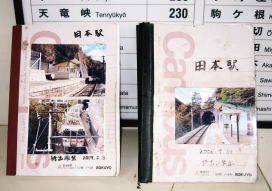|
J R 飯田線 (沿線) の 旅 S ・ A |
|
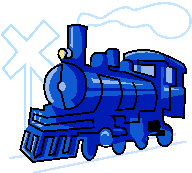 |
|
| 飯田線・歴史の概要 | |||||||||||||||||||
| 伊那谷地域を経由して、信州と三河を結んでいる飯田線は、それぞれの地域の私鉄が、その地に建設を進めた鉄道ルートの統合です。折々の時代の要請のもとに、例えば、ダム建設の資材輸送のために、あるいは戦時輸送のためにと、険しい山岳地帯を貫く工事が行われ、駅が造られましたが、戦時の1943年(昭和18年)に、私鉄の各4社(伊那鉄道・三信鉄道・鳳来寺鉄道・豊川鉄道)が統合、国有化され飯田線が成立します。旧国鉄路線としては駅間距離がとても短いのも、その統合の歴史からくる特徴で、辰野駅から豊橋駅まで実に94駅。約6時間に及ぶ道程は、天竜川、りんご畑、秘境駅など見所が多く、飽きることがありません。 |
|||||||||||||||||||
| 辰野駅・辰野町 松尾峡 | |||||||||||||||||||
| 飯田線上りの始発駅にして、江戸時代からの蛍の名所です。名所となった理由(わけ)は、蛍やカワニナを育てる天竜川の存在で、特に松尾峡と呼ばれる渓谷付近では、以前、町の古老に伺う機会があったのですが、「あそこに立っている木が蛍で火の玉のようだった」というほどです。しかし、それほどの景勝地も昭30年代からは、水が汚れて蛍の数も少なくなってしまいました。 |  |
||||||||||||||||||
| 町は蛍を護るために、あらたに蛍の水路を作ったり、昔からの水路は川幅を広げ、小川のまわりの草を狩り、泥上をして手入れをした結果、今では2万匹といわれる蛍の乱舞が見られるようになりました。6月中旬が見頃です。 ところで、蛍が飛び交う、その時期は、ちょうど近くの入笠山の鈴蘭も見頃を迎えているはずです。そこで、昼間は山の斜面いっぱいに咲く鈴蘭の香りを嗅ぎ、夜は蛍を鑑賞するという贅沢な旅のプランはいかがでしょうか。可憐な日本鈴蘭や、はかなげに舞う蛍の光はきっと貴方を感動させてくれるに違いありません。もし、貴方に想いを伝えたい人がいるならば、是非のこと、この場所に誘うことを、私はお勧めしたいと思います。蛍の光を見ていると人は素直な気持になるものです。一緒に光りを追いかけているうちに、きっと貴方の気持ちは相手に届くことでしょう。運が良ければ、そのとき、ふわりと舞い上がった蛍が髪に留まって髪飾りのように、あるいは、指に留まって、指輪のように光るかもしれません。神様のプレゼントかと思いたくなる、そんな幸せな一瞬が・・・・本当にあるのです。 |
|||||||||||||||||||
| 伊那松島駅・赤そばの里 | |||||||||||||||||||
| 伊那松島駅がある箕輪町は穏やかな町です。青い空、揺れる稲穂、垣根に絡む真っ青な朝顔の花、どこを見ても日本的な田園風景が広がっています。そんな秋の箕輪町に出現するのが、ルビー色のそばの畑!「赤そばの里」と呼ばれる美しい空間です。 日本のそばの花は白ですが、原産地の雲南省からヒマラヤにかけては、ピンクや赤色のそばの花があるのだそうです。1987年、信州大学の氏原教授が標高3800mの高地から持ち帰り、品種改良を重ねてできたものが「赤そば」と呼ばれる「高嶺(たかね)ルビー」という品種で、ルビーに似た、紅い花を咲かせます。信大の農学部が近くにある関係で、赤そばの畑はここらではよく見かけます。しかし、この「赤そばの里」が素敵なのは、そばが深い林に囲まれた扇形の斜面に一面に植え付けられているために、入り口を1歩入ると、町の気配がすっかり無くなり、まるで非日常の空間にいるような気分に浸れることなのです。本当に、ただ、ただ、ルビー色の絨毯が広がっています。赤とんぼが群れ飛ぶ香り高い畑の中では、写真を撮る人、スケッチをする人、ベビーカーや車椅子を押す人に犬を散歩させる人。めいめいが、好きなことをしていて、それを見ると、生きとし生けるもの、みんなこういう気持の良い空間が好きなのだなあと、ほのぼのしてきます。もし、機会があったら、貴方も立ち寄ってはみませんか?遠くにいる家族や友人の顔が自然に浮かんできて「一緒に見たいな」と思うはずです。9月末が見頃です。 |
|||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||
| ★ 赤そばの里 | ★ 箕輪町 もみじ湖周辺 | ||||||||||||||||||
| 伊那駅・高遠 | |||||||||||||||||||
| 高遠城址の桜紅葉を見ようと話が決まり、伊那駅で降りることにしました。10時28分、伊那駅到着です。駅前には老舗の菓子屋があり、そのたたずまいが、この町も何か歴史が古そうだと思わせますが、ぶらぶらする時間もないままに、すぐにバスに乗り、山を上り、25分で終点の高遠駅(バス停の名)に到着です。 古い造り酒屋や旅館が並ぶ内藤氏3万3千石の城下町は静かなものでした。この高地に立って天を仰ぎ見ると、彼方に中央アルプス、こちらには南アルプスが望めて「高遠」という地名が何とはなしに納得がいきます。 高遠城址に行ってみました。春には空が見えないほどにあでやかに咲く桜ですが、今は赤褐色に葉を染めて、静かに余生を送っているという風情の桜たちです。あちこちに植えられた楓の真っ赤な葉も桜紅葉に色を添えて、落ち着いた秋の城址風景が観賞できました。 ところで、ここに植えられている小彼岸桜は、大政奉還の後に、旧藩士たちが泥と汗にまみれて移植したものだと言われています。時代の流れとはいえ、職もプライドも失った藩士たちの心境は、いかばかりだったのでしょう。あるいは、無心の作業に救われる思いだったのかもしれません。こういう話は「天下一の桜」と謳われて人でいっぱいになる春よりも、秋の方が胸に染みます。 |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
| 城址を出て、絵島囲み屋敷を見学しました。1714年(正徳4年)7代将軍家継の生母、月光院の代参として6代家宣の墓参りをした江戸城大奧女中絵島は、帰りに芝居見物をして帰城時間に遅れます。絵島は、公務をおろそかにした罪で高遠藩に流罪となり、罪人として28年間をこの地で送りました。死罪2名、連座した者は1500人。「絵島生島事件」と呼ばれるこの異常な事件は、裏に天映院(6代将軍正室)と月光院(6代将軍愛妾)の確執や8代将軍の跡目争いが絡んでいたと言われていて哀れを誘います。そういえば、かって高遠城が武田氏の拠点だった時代に、織田方によって滅ぼされた武士の血が、今も小彼岸桜を濃いピンクに染めるのだ、という言い伝えもこの地にあるそうです。真に城の周辺といういものは、数奇な歴史とロマンに満ちているものです。 | |||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||
| ★ 絵島囲み屋敷 | ★ 大変厳しい監視に置かれた罪人用の家 | ||||||||||||||||||
| 伊那大島駅・大鹿村 | |||||||||||||||||||
| 13時11分、2両編成で伊那駅を出発しました。列車はりんご畑を縫うように走り、留まっては、また、走ります。14時11分、南アルプスの登山口である伊那大島駅へ到着。 目的の天竜峡駅まで、あと小1時間。この間に、ここからバスで50分、南アルプスの麓にある大鹿村という村をご紹介しましょう。 大鹿村という名を知ったのは、「隠れ里」と題した雑誌の特集だったと思います。南北朝の時代に、後醍醐天皇の第8皇子、宗良(むねなが)親王が北朝と戦うための本拠地としたのが、大鹿村の大河原という地区だったと伝えられています。今はバスで50分ですが、少し前には2時間かかった村のことです。どんなに厳しい場所にあるのか、ご想像いただけると思います。数年前にこの村を訪ねたときには、片側断崖絶壁の九十九折りを、いやと言うほど上っているうちに、緊張でへとへととなり、到着したときにはくたびれ果てて「隠れ里とはこのことか」と思い知った気がしたものでした。 この村には240年もの昔から、歌舞伎が伝わっています。こんなに不便な村にどうして歌舞伎?と思いますが、古道を通じて都の文化が入っていたのだそうです。かって厳しい生活を強いられた山国の人々にとって、歌舞伎は、どんなにか日々の生活に彩りを添えてくれるものだったことでしょう。説明を聞いている私の心まで温かくなるようでした。私たちが訪れたのは、秋の公演が終わった直後で、村の人が指を指しながら「あの回り舞台で演じたのだ」と、教えてくれましたが、周囲はそれは見事な紅葉で、この季節にこういう場所でする歌舞伎なら、演者も見物人もさぞ気持ちが良いに違いないと、長い伝統に納得がいった思いでした。 ところで、この村には不思議なことがあって、何と塩水が湧いているのです(だから隠れ里になったと言われていますが)。湧く理由は解らないのだそうですが、大きな鉄鍋に塩水を入れて、かまどで焚き、煮詰めて塩を作っています。鍋にこびりついた結晶を舐めさせてもらいましたが、甘ささえ感じる、それは美味しい味でした。「塩の直売所」というところで、売っています。ほかにも、大池高原(標高1500m)では、幻の花と言われるヒマラヤの青いケシが栽培されていて、いろいろと、興味の尽きない大鹿村です。 |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
| 天竜峡駅・天竜下り | |||||||||||||||||||
| 15時6分、本日の最終駅と決めた天竜峡駅に到着!新宿からの乗車時間は5時間に及びました。 駅のホームに立って前方を見ると、一方には蛇行しながら三河方面に流れる天竜川の姿が。そして、もう一方には、そうはさせじ、とばかりにそびえ立つ断崖が! 断崖の高さは60mもあり、断崖の中ほどには、地元の人が「塩の道」と呼ぶ(獣道のような)三州街道が通っています。飯田線は、その三州街道に添うように敷かれていて、物資輸送が地元民の悲願だったことが伺いしれます。さらに、飯田線はトンネルの数が108で、その殆どがここから先にあるそうですから、その難工事ぶりも想像できよう、というものです。 さあ、天竜下りです。舟の発着場は駅のすぐ下です。朝から電車に乗っていて私も疲れました。ここはゆっくり舟の人となり、マイナスイオンを浴びて、元気を回復したいと思います。ここから先は写真のみの掲載ですが、お許しいただき、ご一緒にマイナスイオンを感じていただけたら幸いです。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2日目 | |||||||||||||||||||
| 田本(たもと)駅は、行き方も造られた理由もよく解らない駅でした。 田本駅は全国秘境駅ランキング第4位です。飯田線には他に小和田駅という秘境駅もありますが、こちらは皇太子のご成婚のときに大ブームになったので、ご存じの方も多いかもしれません。 ところで、田本駅ですが、ここに行くのは大変でした。「電車に乗ってそのまま行けばいいじゃないの」と、お思いでしょうが、まず、①辰野方面からの電車は天竜峡止まりが多く、乗り換えの時間的ロスが多い。②仮に行けても田本駅で降りたら、こんどは天竜峡に戻るための下りの電車が来ない。 そんなわけで、さんざん検討した末に出した結論は、結局、宿からタクシーを使うこと!まあ、その間の顛末については、走り書きのメモがありますので、それをお読みになってみてください。途中、いやに感傷的な記述があるのは、「遭難」などという言葉が頭をよぎった場所に違いありません。それにしても経験者のいうことには従うものですね。「やめた方がいい」と言ってくれた天竜峡駅の駅員さんの顔が道々何度も頭に浮かびました。 |
|||||||||||||||||||
| 2日目のメモ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 旅の終わりに | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||