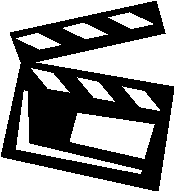 |
NHK僪儔儅偺晳戜偵徻偟偔側傝傑偟傚偆丅 | 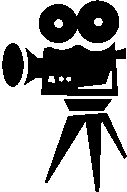 |
|
| 丂09擭丒NHK挬偺楢懕僪儔儅乽偮偽偝乿偺愳墇 丂丂丂 | ||
 |
1457擭丄娭搶娗椞偑屆壨岞曽丒懌棙惉巵偵懳峈偡傞偨傔偵壠恇偺懢揷摴恀丒摴燇晝巕偵柦偠偰偮偔傜偣偨偺偑愳墇忛偺婲尮偱偡丅愴崙帪戙偵偼偙偺忛傪弰偭偰壗搙偐峌杊傕偁傝傑偟偨偑丄摽愳壠峃偑娭搶偵堏傞嵺偵愳墇偵廳恇偺庰堜廳恇傪偁偰偨偙偲偱丄偙偺忛壓挰偼戝偒偔敪揥偟偰偄偒傑偡丅偙偲偵愳墇斔庡丒徏暯怣峧偺帪戙偵偼丄栰壩巭梡悈奐嶍丄愳墇忛壓偺忋壓廫働挰惂搙壔丄愳墇嵳傝奐巒丄愳墇奨摴偲怴壨娸廙塣乮偟傫偑偟偟傘偆偆傫乯惍旛側偳偱丄恖傃偲偺惗妶偼戝偒偔曄壔偟傑偟偨丅挰恖偼偙偺怴壨娸廙塣偱暔帒傪峕屗偐傜塣傃丄偁傞偄偼愳墇偺摿嶻傪峕屗偵塣傫偱丄嵿傪拁偊偰偄偒傑偟偨丅愳墇偼乽峕屗偺杒偺庣傝乿偱偁傝丄乽峕屗傊偺暔帒嫙媼抧乿偲偟偰摽愳枊晎偐傜廳梫帇偝傟丄廫幍枩愇偺忛壓挰偲偟偰尰嵼偵宷偑傞斏塰傪傒傞偺偱偡丅 愳墇偐傜偼屻偵榁拞丄戝榁奿丄戝榁側偳丄枊晎偺梫怑偵偮偄偨斔庡傕懡偔弌偰偄傑偡丅 |
|
 |
搶晲搶忋慄丂丂抮戃偐傜愳墇墂丂丂丂媫峴俁侽暘 俰俼嶉嫗慄丂丂丂怴廻偐傜愳墇墂丂丂丂捠嬑夣懍49暘 惣晲怴廻慄丂丂怴廻偐傜杮愳墇墂丂 媫峴偱侾帪娫 乮傂偲偔偪僐儊儞僩乯 杮愳墇墂偐傜彫峕屗弰夞僶僗偑弌偰偄傑偡丅忔傝崀傝帺桼偱1擔僼儕乕忔幵寯500墌 戝曄恊愗側夝愢傪偟偰偔傟傑偡丅丂 |
|
 |
拠挰岎嵎揰偐傜杒偵岦偐偭偰嶥偺捯岎嵎揰傑偱傪乽憼憿傝偺挰暲傒乿偲屇傃丄愳墇傪戙昞偡傞娤岝柤強偱偡丅崙廳梫揱摑揑寶憿暔孮曐懚抧嬫乮1999巜掕乯丅 嶥偺捯嬤偔偵偁傞戝戲壠廧戭乮崙廳暥乯偑侾俉俋俁乮柧帯26擭乯擭偺愳墇戝壩偺偲偒偵從偗巆偭偨偙偲傪偒偭偐偗偵丄憼憿傝廧戭偑偙偺抧堟偵懡偔憿傜傟傑偟偨丅崱傕懡偔偺憼憿傝偺壠偑巆傝丄旤偟偄挰暲傪屩偭偰偄傑偡偑丄戝壩屻偺1893擭偵寶偰傜傟偨愳墇斔屼梡払偺榁曑壻巕曑乽婽壆乿偼懗憅乮壩嵭偺椶從偐傜曣壆傪傑傕傞傕偺乯傪帩偮傕偺偲偟偰偼尰懚偡傞桞堦偺傕偺偲偟偰堦尒偺壙抣偑偁傝傑偡丅拠挰岎嵎揰妏偵偁傝傑偡丅 (傂偲偔偪僐儊儞僩) 婽壆偺戙昞揑側柫壻乽婽偺嵟拞乿乽婽偳傜乿偼忋昳側娒偝偱丄偲偰傕旤枴偟偔丄愄偐傜庤搚嶻偵帩偭偰峴偔偲婌偽傟偰偄傑偟偨丅傑偨丄堭偣傫傋偄傗丄堭偺娒彄偁傜傟偼丄彫偝偄偙傠偐傜丄偍傗偮偲偟偰怘傋偰偍傝丄椢拑偩偗偱側偔丄峠拑傗噗噼偵傕傛偔崌偄傑偡丅 |
|
 |
||
 |
崅偝侾俇丏俀倣偺愳墇偺儔儞僪丒儅乕僋偱偡丅愳墇斔庡丒庰堜拤彑偺偙傠偵偮偔傜傟丄偦偺屻戝壩偱從幐偟丄徏暯怣峧偺偲偒偵嵞寶偝傟傑偟偨丅侾俉俋俁乮柧帯26擭乯擭偺愳墇戝壩偱傕從幐偟傑偟偨偑丄梻擭丄愳墇偺拻暔巘偵傛偭偰峕屗帪戙偦偺傑傑偵嵞尰偝傟傑偟偨丅旤偟偄巔偼峕屗摉帪偺傑傑偵丄崱偱傕1擔偵4夞丄帪傪抦傜偣傑偡丅暯惉8擭偵娐嫬挕傛傝乽巆偟偨偄擔杮偺壒晽宨100慖乿偵傕慖偽傟傑偟偨丅 (傂偲偔偪僐儊儞僩) 戝夾擔偺栭嬻偵嬁偒傢偨傞乽帪偺忇乿偺壒傪暦偒側偑傜丄婌懡堾偵弶寃偵岦偐偆抧尦柉傕懡偔丄巹傕偦偺偆偪偺堦恖偱偟偨丅巕嫙偺帪偐傜暦偄偰偄傞帪偺忇偺壒偼丄桪偟偄壒偱丄怱傪棊偪拝偐偣偰偔傟傑偡丅 |
|
 |
峕屗帪戙丄梴庻堾偺栧慜挰偲偟偰塰偊偨応強偵偁傝傑偡丅 柧帯偺弶傔丄楅栘摗嵍塃塹栧偑偙偺抧偵廧傫偱懯壻巕傪惢憿偟偨偺偑巒傑傝偲偄傢傟偰偄傑偡丅柧帯偺屻敿偐傜偺傟傫暘偗偵傛偭偰師戞偵揦偑憹偊丄戝惓12擭偺娭搶戝恔嵭偱從偗弌偝傟偨恄揷丒愺憪丒嬔巺挰偺壻巕栤壆偑偙偺抧偵堏偭偰偒偨偙偲偱偝傜偵惙傫偵側傝傑偟偨丅嵟惙婜偺徍榓弶婜偵偼70梋揦偑揦傪楢偹偰偄偨偦偆偱偡丅 乮傂偲偔偪僐儊儞僩乯 尰嵼丄壻巕壆偼20悢揦丅嵟惙婜偵妑傋傞偲彮側偄傛偆偱偡偑丄楢擔懡偔偺娤岝媞偱擌傢偭偰偄偰嬃偒傑偡丅嬥懢榊埞丄悈埞丄僛儕乕價乕儞僘丄曄傢傝嬍丄惗汭摐丄屲壠曮倕倲們丄懡偔偺庬椶偺壻巕偼尒偨栚傕壺傗偐偱妝偟偔丄偟偐傕揱摑偁傞揦偑庤嶌傝偡傞偺偱偡偐傜丄旤枴偟偄偙偲傕栜榑偱偡丅 嬤偔偺僿儖僗丒僙儞僞乕偵妡偐傞戝廜墘寑偺堦嵗偑丄幣嫃弶擔偺搚梛擔偵偼偙偙傪楙傝曕偔偦偆偱偡丅偦偆偄偆弾柉揑偱妝偟偄暤埻婥偑偙偙偺椙偄偲偙傠偱偡丅 |
|
 |
||
 |
偙偺嵳傝傪岅傜偢偟偰丄愳墇偼岅傟傑偣傫丅 尦棃偼愳墇偺憤捔庣丄昘愳恄幮偺嵳楃峴帠偵桼棃偟傑偡偑丄愳墇斔庡丒徏暯怣峧偑昘愳恄幮傊恄梎傗嵳楃梡嬶傪婑恑偟偰嵳楃傪彠椼偟偨偙偲傪偒偭偐偗偵尰嵼偵宷偑傞愳墇嵳傝偑巒傔傜傟偨偲偄傢傟偰偄傑偡丅1698擭偵弶傔偰梮傝壆戜偑偱偰埲棃丄擭乆惙戝偵側傝丄揤曐擭娫偵偼摉帪偺愳墇廫箳瑐穫讉膫獛R幵偺忋偵恖宍傪偺偣傞傛偆偵側偭偨偦偆偱偡丅 尰嵼偼10寧偺戞嶰搚丄擔偵峴傢傟偰偄傑偡丅 嶥偺捯嬤偔偵嵳傝夛娰偑偁傝丄嶳幵傪尒傞偙偲傕偱偒傑偡偑丄儕傾儖僞僀儉偱尒傞嶳幵偵偼偐側偄傑偣傫乮嵍偺幨恀乯 (傂偲偔偪僐儊儞僩) 愄偐傜抧尦偺恖偵垽偝傟懕偗偰偒偨嵳傝偱丄愳墇嵳傝偺帪婜偵側傞偲丄奨拞偑愳墇嵳傝堦怓偵愼傑傝傑偡丅尒強偼栭偵峴傢傟傞乽塯偭偐傢偣乿偱偡丅栭偺奨偵嶳幵偲嶳幵偑岦偐偄崌偄丄偍殥巕傗梮傝偺嫞墘傪峴偆帪偵偼丄嶳幵偺傑傢傝偵戝惃偺恖偑廤傑傝傑偡丅埿惃偺偄偄妡偗惡傗丄偍殥巕傪暦偄偰偄傞偲丄尒偰偄傞恖偺婥暘傕惙傝忋偑偭偰偒傑偡丅摿偵丄憼憿傝偺挰暲傒傪嶳幵偑捠傞巔偼埑姫偱偡丅 |
|
丂 |
1301擭偵偼娭搶揤戜廆580梋帥偺杮嶳偲側傝丄娭搶揤戜嫵妛偺拞怱偱偟偨偑丄峕屗帪戙偵丄屻偵弎傋傞婌懡堾偺揤奀偑壠峃偺怣棅傪摼傞偲丄拞怱偼婌懡堾偵堏傝丄尰嵼偼娭搶敧抙椦偺堦帥堾偲側偭偰偟傑偄傑偟偨丅嫹嶳拑敪徦偺抧偩偦偆偱偡丅 乮傂偲偔偪僐儊儞僩乯 戝曄偨偨偢傑偄偑旤偟偄帥偱偡丅嫬撪偵尒忋偘傞傛偆側嬥栘嵰偺栘偑偁傝丄婫愡偑崌偆偲丄枮揤偺惎偺傛偆偵嶇偔嬥怓偺嶱偺壓偱嬌妝忩搚偵棃偨偐偺傛偆側娒偄崄傝傪歬偖偙偲偑偱偒傑偡乮枮奐偼10寧10擔慜屻偐丠乯丅掚傕忇極傕慺揋偱偡丅 |
|
 |
愳墇戝巘 帨娽乮偠偘傫乯戝巘揤奀偑摽愳壠峃偺怣擟傪摼傞偲丄拞堾偵戙傢偭偰媫敪揥偟偨帥偱偡丅乽杒堾乿偲屇偽傟偰偄傑偟偨偑丄1612擭偵壠峃偐傜乽搶塨嶳婌懡堾乿偺柤傪偆偗丄1613擭偵偼娭搶揤戜廆580梋帥偺杮嶳偲偝傟傑偟偨丅 嫬撪偵峕屗忛偐傜堏抸偝傟偨寶暔偑偁傝丄3戙彨孯壠岝庤怉偊偺乽巬悅傟嶗乿乽壠岝抋惗偺娫乿弔擔嬊偺乽壔徬偺娫乿側偳丄尒強傕懡偔偁傝傑偡丅 乮傂偲偔偪僐儊儞僩乯 弶寃丄偍媨嶲傝丄幍屲嶰丄側偳偱堦擭拞擌傢偭偰偄傑偡丅 峕屗忛偐傜堏抸偝傟偨寶暔偼掚傕旤偟偔丄嶗偺婫愡偵掚傪尒側偑傜晽偵悂偐傟傞偺傕椙偄偲巚偄傑偡丅 |
|
 |
婌懡堾偺晘抧撪偵偁傝傑偡丅 峕屗帪戙丄婹閇傗幮夛晄埨傪攚宨偵朙忰婩婅丄巕懛斏塰側偳傪婅偭偰偙傟傜偑憿傜傟偨偲峫偊傜傟偰傑偡丅拞偵侾懱偼帺暘偺婄偵帡偨傕偺偑偁傞丄偲尵傢傟偰偄傑偡丅 乮傂偲偔偪僐儊儞僩乯 梾娍偺拞偵偼柧帯弶婜偺攑暓毷庍塣摦偱毷偝傟偰晄姰慡側傑傑偺傕偺傕偁傝傑偡丅戝偒側帪戙偺棳傟偺拞偱丄弾柉偺婅偄偱偁傞偙偆偄偆傕偺偑娙扨偵毷偝傟偰偟傑偭偰巆擮偱偡丅 |
|
| 乣丂斣奜曇丂乣乣丂 偳偙傊峴偭偰傕峕屗傪姶偠傞愳墇偱偡偑丄尰戙偭巕傕尦婥偵傗偭偰偄傑偡丅 俿倁傗塮夋偱桳柤偵側偭偨丄偛懚偠乽僂僅乕僞乕儃乕僀僘乿偺偛徯夘偱偡丅 |
||
 丂 丂 |
僂僅乕僞乕儃乕僀僘偺儌僨儖偲側偭偨妛峑偱偡丅抧尦偱偼丄乽愳崅(偐傢偨偐)乿偺垽徧偱恊偟傑傟偰偍傝丄暥壔嵳偺棃応幰偼侾枩恖傪挻偊傑偡丅 悈塲晹偑斺業偟偰偄傞乮偛懚偠乯僔儞僋儘偼丄慡堳偺墘媄偑懙偭偰偄偰偄傞偽偐傝偱側偔丄僄儞僞乕僥僀儊儞僩惈傕崅偔丄抝惈僠乕儉側傜偱偼偺敆椡傕偁偭偰尒偰偄傞恖傕巚傢偢庤攺巕傪偡傞傎偳丅摿偵丄壗抜偵傕廳側傞楨偑姰惉偡傞弖娫偼丄戝偒側娊惡偑両両両 戝曄夰偐偟偔丄崱偲側傞偲婱廳側巚偄弌偱偡丅 |
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
| 俶俫俲丂俀侽侾侽擭戝壨僪儔儅乽棿攏揱乿偺晳戜丂丂崅抦 | ||
| 棿攏 丂俬俶 搚嵅 |
 |
嶳撪壠恇偑廧傓崅抦忛壓偼丄忛傪拞怱偵忋巑偺廧傓妔拞偲丄嫿巑傗懌寉偑廧傓忋挰丒壓挰偵暘偐傟偰偄傑偟偨丅嶁杮棿攏偼丄侾俉俁俆擭乮揤曐俇擭乯丄嫿巑傗懌寉丄晲壠曭岞恖偺揁戭偑棫偪暲傇忋挰偵嶁杮壠偺師抝偲偟偰惗傑傟傑偟偨丅孼偺尃暯偺傎偐偵愮掃丄塰丄壋彈偲偄偆巓偑偄偨偦偆偱偡丅 嶁杮壠偺杮壠偼嵥扟壆偲偄偄丄忛壓孅巜偺崑彜偲偟偰抦傜傟偰偄傑偟偨偑丄暘壠偺嶁杮壠傕忋巑傪憡庤偵幙彜側偳傪塩傓桾暉側壠偱偟偨丅椞抧崅昐榋廫堦愇敧搇巐彙丅奺抧傛傝椞抧暷偑偁偑傝丄宱嵪揑偵偼壗晄帺桼偺側偄惗妶偩偭偨偦偆偱偡丅 侾俀嵨偺擭丄棿攏偼乽妛栤乿傪巙偟偰帥彫壆偵擖傝傑偟偑丄傎偳側偔戅弇丅師偵乽晲乿傪巙偟偰嬤強偺彫孖棳擔崻栰曎帯偺栧傪偔偖傝傑偡丅寱偺榬傪忋偘傞偙偲偱丄師戞偵帺暘偵帺怣傪偮偗偨偲偄傢傟偰偄傑偡丅 棿攏偼扙斔偡傞傑偱偵俀夞峕屗偵弌偰偄傑偡丅偄偢傟傕寱偺廋峴偺偨傔偱丄愮梩摴応偵擖傝杒扖堦搧棳傪妛傫偱偄傑偡偑丄偙偺俀夞偺峕屗懾嵼偑棿攏偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨偙偲偼憐憸偡傞偵擄偔偁傝傑偣傫丅偙偲偵丄侾夞栚偺峕屗懾嵼拞偵偼崟慏偺棃峲偑偁傝丄戝憶偓偺側偐丄搚嵅斔偼梀妛惗傑偱嬱傝弌偟偰昳愳晅嬤偺寈旛偵偁偨傝傑偟偨丅摉慠丄梀妛拞偺棿攏傕偦偺擟偵偁偨偭偨偲偄傢傟偰偄傑偡偑丄偙偆偄偆宱尡偼丄庒偄棿攏偵愭傪尒悩偊傞姶惈傪攟傢偣偨偵堘偄側偄偱偟傚偆丅傑偨丄奺抧偐傜偺梀妛惗偑峕屗偵廤傑偭偰偄偨偙偺摉帪丄庒幰偨偪偼斔傗恎暘偺忋壓偲偄偆榞傪挻偊偰擬偭傐偔岅傝崌偄丄帇揰傪斔偐傜擔杮傊丄擔杮偐傜奜崙傊偲峀偘偰偄偭偨偵堘偄偁傝傑偣傫丅晻寶帪戙偺廲偺娭學偐傜墶偺娭學偑惗傑傟偰偄偭偨帪婜偱傕偁傞偲巚偄傑偡丅 侾俉俇侾擭乮暥媣尦擭乯丄偝偝偄側岥榑偑偒偭偐偗偱丄屻偵乽塱暉帥栧慜帠審乿偲屇偽傟傞丄忋巑偲壓巑偺恘彎帠審偑婲偙傝傑偡丅壓巑懁偵晄棙偺傑傑堦墳偺寛拝偑偮偗傜傟偨偙偺恘彎帠審偼丄擔崰偔偡傇偭偰偄偨忋巑偲壓巑偺懳棫偵桘傪偦偦偄偩宍偲側傝丄搚嵅嬑墹搣寢惉偺暁慄偺傂偲偮偵側偭偨偲偄傢傟偰偄傑偡丅偙偺擭偺俉寧丄晲巗敿暯懢丄搚嵅嬑墹搣寢惉丄俋寧偵偼棿攏偑搚嵅嬑墹搣壛柨丅 侾俉俇俀擭乮暥媣俀擭乯丂棿攏俀俉嵨丂戲懞憏擵忓偲偲傕偵搚嵅斔傪扙斔両両両 堦愢偱偼晲巗敿暯懢偲峫偊偑憡梕傟側偐偭偨偲傕尵傢傟偰偄傑偡偑丄扙斔偲偄偆廳嵾傪斊偝側偗傟偽側傜側偐偭偨柧妋側棟桼偼尒偮偐偭偰偄傑偣傫丅偟偐偟丄搚嵅偐傜埳梊傊敳偗偰悾屗撪奀傪搉偭偨棿攏偺娽嵎偟偼丄偒偭偲悾屗撪奀偺偢偭偲愭傪尒悩偊偰偄偨偵堘偄偁傝傑偣傫丅傑偙偲偵棿攏偼晲巗敿暯懢偑搚嵅曎偱昞尰偟偨捠傝偺乽偁偩偨傫乮廂傑傝偒傟側偄乯搝乿偩偭偨偲偄偆偙偲側偺偱偟傚偆丅 棿攏偺恖惗偺戝偒側揮婡偲側傞彑奀廙偲偺弌夛偄偼丄偙偺擭偺廐偺偙偲偱偡丅 |
| 棿攏憸 丂IN 宩昹 |
 |
徍榓3擭偵姰惉偟偨丄崅偝俆丏俁倣丄戜嵗傪擖傟傞偲侾俁丏係倣偺崅偝偺戝偒側憸偱偡丅 暦偙偊偰偔傞戝偒側攇偺壒偑偲偰傕報徾揑偱偟偨丅 墶昹偱惗傑傟堢偭偨巹偵偲偭偰偼丄懢暯梞偺戝偒側暽偄奀偺峀偑傝傕丄 傑偭偡偖偵懕偔敀偄嵒昹傕丄懪偪婑偣傞崅偔敀偄攇傕丄棫偪暲傇徏偺栘乆傕丄慡偰偑怴慛偱旤偟偔姶偠傜傟傑偟偨丅 棿攏憸偼丄偦傫側宩昹傪尒壓傠偡崅戜偵寶偭偰偄傑偡丅 幨恀傗塮憸偱偼偍撻愼傒偺偙偺憸偱偡偑丄幚嵺偵栚偺摉偨傝偵偡傞偲丄尒忋偘傞崅偝丄偦偺僗働乕儖偺戝偒偝偵埑搢偝傟傑偟偨丅 偳偙傑偱傕懕偔戝偒側奀ゥ眰虋C偑辍偐奜崙偲偮側偑偭偰偄傞偙偲傪姶偠側偑傜丄棿攏偼枊枛偺帪戙傪夁偛偟偰偄偨偺偱偟傚偆偐ゥB 2010擭偺戝壨僪儔儅偺庡恖岞丄娤岝媞偱擌傢偄偦偆側偙偺抧偱偡偑丄傑偨朘傟偨偄偲巚偄傑偟偨丅 |
| 塮夋丄俿倁 偺棿攏 |
 |
愴慜傕棿攏偺塮夋偼嶌傜傟偰偄傑偡偑乮斅搶嵢嶰榊側偳乯丄愴屻丄棿攏偑偙傟傎偳桳柤偵側偭偨偺偼丄傗偼傝丄巌攏椛懢榊偑僒儞働僀怴暦偵宖嵹偟偨乽棿攏偑備偔乿偱偼側偄偱偟傚偆偐丅徍榓俁俈擭俇寧偐傜巒傑傝丄係侾擭俆寧偵姰寢偟偰偄傑偡丅 塮夋偱傕丄愴屻丄桳柤攐桪偑棿攏傪墘偠偰偄傑偡偑乮愇尨桾師榊丄拞懞嬔擵彆側偳乯丄俶俫俲戝壨僪儔儅偵尷偭偰傕懡偔偺攐桪偑墘偠偰偄傑偡丅 徍榓係俁擭戝壨僪儔儅乽棿攏偑備偔乿偱丄杒戝楬嬘栫偑棿攏傪丄傑偨丄乽彑奀廙乿偱摗壀峅丄乽壴恄乿偱壞敧栘孧丄乽隳傇偑偛偲偔乿偱嵅摗峗巗偲丄摉戙偺恖婥攐桪偑偦傟偧傟偵棿攏傪墘偠偰偄傑偡丅偳偆偟偰丄偙傫側偵棿攏偼恖婥偑偁傞偺偱偟傚偆丅 巚偆偵丄 嘆扙斔偲偄偆廳嵾傪斊偟偰傕斔偺奜偵弌偰偄偒偨偐偭偨恑庢偺婥惈丄嘇彑奀廙偺傛偆側戝暔偐傜傕抦嬾傪摼傞恖娫揑枺椡丄嘊巑偱偁傝側偑傜奀墖戉傪寢惉偟偰棙傪捛媮偡傞廮擃惈丄偁傞偄偼崌棟惈丄嘋嶧挿楢崌偺晍愇傪晘偔偲偄偆惌帯揑僙儞僗丄嘍棿攏傪庢傝姫偔彈惈丄偦偟偰丄嵟屻偵丄嘐堐怴傪慜偵偟偰旕嬈偺巰傪悑偘傞斶寑惈丅偙偆偄偆條乆側僉乕儚乕僪偑棈傒崌偭偰丄棿攏偼崱傕恖乆傪枺偣傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 俀侽侾侽擭丄暉嶳夒帯偼偳傫側棿攏憸傪尒偣偰偔傟傞偺偱偟傚偆偐丅暉嶳僼傽儞側傜偢偲傕婜懸偟偨偄偲偙傠偱偡丅 |
| N丒O丂丂A丒H 幨恀嫤椡丂丂A |