 |
モーツアルトの狂気 原田 勉 |
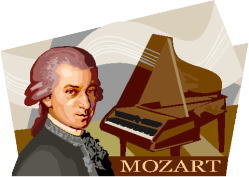 |
| 1 |
先日ある方にオペラサロンに連れて行っていただく機会があった。そこは食事を楽しみながら若手声楽家の歌曲を聴くことができる。ピアノ伴奏で3部構成。この晩はソプラノ、メゾソプラノ、テノールの3人の若手声楽家の熱演であった。 私が一番驚いたのはプロの声楽家の声量である。サロンなので音響機器は全く使わずに歌を聴かせてくれるのであるが、一人で優に我々の十人か二十人分の声量である。それを聴いてかねてからの疑問が氷解した。 モーツアルト作曲の「フィガロの結婚」のエンディングは登場人物全員が合唱するが、ソロの受け持ちのある演者は全部でわずか11人である。私はエンディングのシーンがこの少人数で大合唱のように聞こえることが不思議でならなかったのであるが、一人一人がこの声量であれば11人もいれば大合唱のように聞こえるはずである。このことがやっと分かった。 |
| 2 |
この晩サロンの演目の中で女性二人が「フィガロ」から「お先にどうぞ」のデュエット(ソプラノとメゾソプラノ)を演じてくれた。歌も素晴らしかったが、誠に見事な演じ方であったのに感心した。 「フィガロ」と言えば、今から5年近く前のまさにこの欄にこのオペラを聴きに行った駄文を載せていただいたことがある。そのときこの作品について書こうと思いながら断念したことがあるので、今回はせっかくの機会なので、少し書かせていただくことにする。何といっても音楽・芸術に関して全くの素人が言いたい放題なので、独断と偏見に満ちていることを最初にお断りしておきます。関係者の方は怒らないで読んで下さい。 |
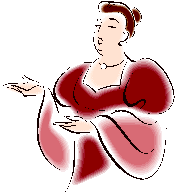 |
| 3 |
私が「フィガロ」を聴いたのは40歳を過ぎたころかもう少し前だったと記憶している。私が愕然とさせられたのは「自分は40年も生きてきて、どうしてこんな面白い作品を知らなかったのであろうか」ということである。「今までなんという無駄な人生を送ってきたのか」。"おまえの人生など初めから無駄ばかりだ"と言われてしまえば反論のしようもないが、それなりにクラシック音楽にしても優れた作品は聴いているつもりだった自分は、オペラがこんなに面白いものだとは全く知らなかったので、そのことがショックだった。どうして自分はオペラを知らなかったのか、その理由を考えてみると、それは「学校教育で扱われないからだ」と思った。「学校の授業は真面目に出ていましたよ」と自慢する気持ちは毛頭ないし、高校の音楽の時間は例外なく睡眠をむさぼっていたようにも記憶しているが、少なくとも私の通った学校の先生方の中に「オペラはこんなに面白いものだよ」と教えて下さる方はいなかったように思う。 ただし学校教育で扱わないというのは無理もないことである。オペラは学校教育には決定的に適していないからである。「フィガロ」に限らず人気のあるオペラは例外なく、三角関係・不倫・殺人など不道徳と犯罪のオンパレードだ。学校の先生が生徒に対して「この人はどうしてこういう歌を唄っているのか」、「この場面はこれこれの意味である」などと解説するのは殆ど不可能な内容ばかりである。椿姫や蝶々夫人の「職業」を清く正しい子どもたちには教えられない。オペラというものは酒と同じく未成年者に禁じられた娯楽であって、オペラの楽しさは大人になってから自分で知るしかない。酒であればたしなむ人の数が多いからそれを知らずに過ごすことはあり得ないが、オペラはそうではないから、私はオペラの味を知らずに馬齢を重ねてしまった、ということだ。 |
| 4 | 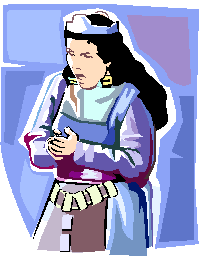 |
現在一般に演じられているオペラの中で最も古い作品が「フィガロ」だが、その「フィガロ」はスキャンダル満載の作品である。一言で言えば好色な殿様が事件を引き起こし、最後にその殿様がやりこめられてしまう喜劇である。当時の庶民にしてみればやんやの喝采ものである。特に象徴的なのが2幕目で、幕が開くといきなり奥方の寝室で、奥方が薄物をまとって物憂げにアリアを歌う場面から始まる。このあたりの演出は心憎いばかりである。 |
| 5 |
それで、このように「フィガロ」は『不道徳な作品』だと思いながら鑑賞をしていて、「モーツアルトは狂っている」と思った。 「フィガロ」は音楽史上燦然と輝く星である。世紀のヒット曲満載だ。いつの時代でも誰もが口ずさむ有名曲が目白押しであって、天才モーツアルトの面目躍如たるものである。しかしその「ヒット曲」は悉く歪んだ感情に裏づけられ、または歪んだ感情を表現するものである。 1幕目最後のフィガロの「もう飛ぶまいぞ、この蝶々」、これは「いじめ」「虐待」の歌だ。殿様にいたずらを見咎められ罰として軍隊送りを命じられた傷心のケルビーノに対してフィガロが唄う歌だが、ケルビーノは紅顔の美青年、軟弱な色男であって、軍隊になんか絶対に行きたくない、行ったら死んじゃう、ボクはもっと女の子と一緒にいたいよ、と思っているのに、フィガロはそんなケルビーノを半分からかって「軍隊に行け」と唄うわけで、これは傷に塩を塗り込む歌、死者を足蹴にする歌だ(この歌の場面でケルビーノが元気になってオイチニイ、オイチニイ、と勇んで行進を始める演出の作品があるが、その演出は間違っていると私は思う。ここはケルビーノがフィガロのいじめに耐えきれずに泣き出すのが正しい。こちらの演出の上演の方が多いと思う)。 ケルビーノの1幕目と2幕目の有名なアリア2曲はどちらも、思春期の男子が「女性」というものに対して抱く妄想をストレートに唄う歌である。「恋愛」などという上等なものではなくて、もっと本能的な欲望を恥ずかしげもなくあからさまに唄っている。 3幕目の奥方とスザンナの「手紙」の二重唱。これまた誠に美しい歌だ。映画「ショーシャンクの空に」で図書館係になった主人公が刑務所でこのレコードをかけ、囚人たちがうっとりと聞き惚れるシーンが有名だ。確かに囚人たちでも言葉を失うほどの美しい曲だが、その内容は計略・策略・陰謀である。「助平な殿様をだまくらかせて差し上げましょう」という歌である。しかも殿様の好色に乗じて事を運ぼうと企てるのだから本当にたちが悪いと思うのだが、それをモーツアルトは最高に清らかな歌に仕上げた。 4幕目のフィガロの「男たるものは」は嫉妬の歌。嫉妬に狂って、責任転嫁・自暴自棄の歌である。しかも、ついさっきまでフィガロ自身が伯爵を罠に嵌めようと画策していながら、自分で掘った穴に自分で落ちてもがき苦しむ歌である。誠に阿呆で滑稽な男の惨めな姿を描いた歌だ(私はこの歌をこう思うのだが「世の男たちよ、よく見ろ」のところで、会場の照明を明るくした舞台を観たことがある。男性の観客に対する普遍的なメッセージであると言いたいようであったが、私はこれは全く間違った解釈だと思った。この歌でフィガロが言っていることはひとつも正しくないのである)。 |
| 6 | このように生身の人間の最もドロドロした感情、歪んだ感情、一番深いところにある感情に対して、モーツアルトは歴史に残る美しいメロディをつけた。いずれも一度聴いたら忘れることのできない美しい曲ばかりである。「モーツアルトは頭がおかしい」としか考えられない。 |
 |
| どうしてモーツアルトはこんなことをしたのだろうか。 よく言われるのは、例えば次作「ドン・ジョバンニ」の中で人気テノール歌手のために後で追加した歌がつまらない、ということだ。これは恋人に対する想いを切々と唄う歌なのだが、一般には「モーツアルトの歌の中ではつまらない」ということで評価が固まっている。このようにモーツアルトは人間の平凡な感情には創作意欲をかき立てられなかったのではないだろうか。モーツアルトほどの作曲家であれば、どんな詩であっても曲をつけることは自由自在であったはずだ。題材となる歌手の感情が平凡なというか、ありきたりのものであるとモーツアルトの「やる気」が起きなかったのではなかろうか。それに対して、もっとドロドロして、生身の人間らしい感情を表すときに、モーツアルトは創作意欲をかき立てられ、「やる気」を起こして作曲したのではないだろうか。 このように人間の穢らしいというか最も人間らしいというか、生身の人間のドロドロした部分に光をあてて、えぐり出したところが、これぞまさしく芸術というべきだと思うし、こういう芸当をなしえたモーツアルトを「天才」と呼ぶべきだと思う。 |
| 7 | このほかにもこの作品の魅力的なところを書き出せばきりがない。もうひとつ思うのは「モーツアルトはどうしてスザンナというキャラクターを描くことができたのだろうか」ということだ。スザンナこそがこの作品の良心、働き者で、頭が良く、主人に忠実で真っ直ぐで愛すべき我らがスザンナ。こうしたキャラクターの人物をどうして描くことができたのだろうか。ダ・ポンテの台本が素晴らしかったからと言ってしまえばそれまでだが、モーツアルトが一体それまでにどのような体験をしてきたのだろうか、こう考えると、この作品やモーツアルトに対する興味は尽きないのである。 |
| 8 | 最後に「フィガロ」は市販されているCDやDVDが一番多い作品だと思うが、どの演奏映像が一番良いかは難しいところだ。そもそもオペラは、このアーチストにこの役を演じて貰いたい、この人とこの人の共演をぜひ鑑賞したい、と思ってもまず適わないので、「フィガロ」は作品が素晴らしいだけに現実の舞台に対する不満がどうしても残ってしまう。スザンナ役は最初から最後まで殆ど出ずっぱりだから、「大物」のソプラノに演じて貰いたいと思っても無理な注文だ。フレーニが演じたベームの映像があるけれど、あれはスタジオ撮りなので舞台のスリルがないのが不満だし、、、。 |  |
| 私は実は2005年にネトレプコがザルツブルグで演じた作品は手元にあるのだが、演出がショッキングだと言われたこともあり、まだ観ていない。同じアーノンクールの1996年のチューリッヒ歌劇場の舞台(昔NHK-BSで放送された)が一番安心して聴けるかなと思う。これはスザンナ役のイザベル・レイと伯爵夫人役のエヴァ・メイのソプラノ二人が素晴らしい(二人とも美人!)。ソプラノの声質が似ていて美しいです。とにかくアーノンクールは猟奇的に遅いテンポで、私は大好きだ。本当に遅いテンポで序曲が始まるといまでもワクワクしてしまいます。 |