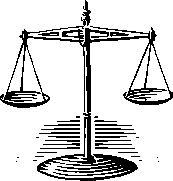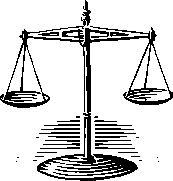|
近年,主に高齢者をターゲットとした詐欺的な投資勧誘事件(未公開株詐欺商法など)が増加傾向にあります。その手口は年々巧妙化しており,相当な注意を払っていても被害に遇ってしまうケースが後を絶ちません。
そのような騙しの手口のひとつとして,金融庁などの国家機関のお墨付きを得ているかのように説明し,被害者を安心させるというパターンがあります。そして,そのようなお墨付があるかのように見せかける手段として,「適格機関投資家等特例業務」という制度が悪用されるケースが少なくありません。
今回はこのあまり聞き慣れない「適格機関投資家等特例業務」の概要と問題点について解説したいと思います。
いわゆる投資ファンドの出資者の募集等を行うためには,一定の要件を備えた上で第二種金融商品取引業等の登録をしなければならないのが原則です。
しかし,適格機関投資家(要は「プロ投資家」のことです)と49名以下のそれ以外の者(以下「適格機関投資家等」といいます)を相手方として行う集団投資スキームの私募や運用は,「適格機関投資家等特例業務」として財務局等への簡易な届出をすれば足りるとされ,第二種金融商品取引業等の登録は不要となります。
そして,特例業務届出者には,金融商品取引業者が従うべき金融商品取引法上の各種規制は一部を除いて適用されません。
(1) 適格機関投資家等特例業務は,もともとはプロ投資家とともにその周辺の関係者らが参加する小規模ファンドを想定し,そのようなファンド投資を促進するために設けられた制度です。
しかし,簡易な届出で足りることや,適格機関投資家以外の者の範囲について49名という形式的な要件しかなくその属性に特に限定がないことに着目した悪質業者が詐欺的な投資勧誘に悪用し,投資経験の乏しい高齢者らが被害に遭うケースが目立っています。
そのような被害者は,業者から「適格機関投資家等特例業務として財務局にきちんと届出をしているので安心です。」などの説明を受け,当該投資ファンドがあたかも公的機関のお墨付きを受けているかのように誤信させられているケースが多いと思われます。届出業者一覧が金融庁のホームページにアップされており,そのこともそのような誤信を助長する一因になっているようです。
悪質業者の中には,適格機関投資家を参加させていない,49名を超える一般投資家から出資を受けるなど,そもそも適格機関投資家等特例業務の要件を満たさずにその届出を行っている者も少なくないようです。
(2) 不当な勧誘を行なった業者等の損害賠償責任が肯定された裁判例
違法な投資勧誘等を行なった特例業務届出業者らの顧客に対する損害賠償責任が認められた裁判例として以下のようなケースがあります。
①京都地裁平成24年4月25日判決(先物取引裁判例集66号357頁)
特例業務届出者が行った集団投資スキーム持分への出資の勧誘につき,49名を超える一般投資家を相手に行っていたとして特例業務該当性を否定し金商法29条違反(無登録営業)を認定するなどして,特例業務届出者やその代表者らの不法行為責任を肯定した
②東京地裁平成24年6月28日判決(ウェストロー・ジャパン)
特例業務届出者が行った集団投資スキーム持分への出資の勧誘等につき,適格機関投資家の参加がないため適格機関投資家等特例業務の特例は適用されない違法な出資の募集であったこと,顧客から募った多額の出資金を運用した実績がないなど不正な処理がされていたことなどを認定し,特例業務届出者やその代表者らの不法行為責任を肯定した
以上のような問題点を踏まえ,国や金融庁等は,内閣府令の改正(届出記載事項に適格機関投資家の名称等の記載を義務づけるなど)や監督指針の改正(届出受理時等のチェック項目を追加するなど)などにより悪用を防ぐための対応強化を図っています。しかし,それでも上記の問題点が完全に払拭されたわけではなく,悪用の危険性は依然として残っていると思います。
もし,本稿をご覧頂いた方が適格機関投資家等特例業務を利用した投資ファンドへの出資の勧誘を受けた場合は,家族や友人など信頼できる方に相談するなど慎重に判断をして頂きたいと思います。
そして,万が一不幸にも悪質な特例業務届出業者の被害に遇われた場合は,速やかに弁護士へご相談されることをお勧めします。
以 上
|