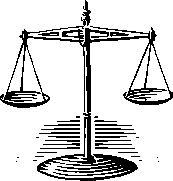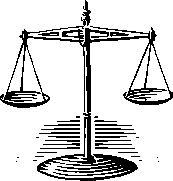改正高年齢者雇用安定法(以下「高年法」といいます。)が、2013年(平成25年)4月1日に施行されました。
|
高年法とは、定年退職者や高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を講じ、高年齢者等の職業の安定や福祉の増進を図るための法律であり(高年法1条。以下、条文は高年法)、公的年金支給開始年齢の引き上げ政策と表裏一体の法律です。
老齢厚生年金の支給開始年齢は、段階的に引き上げられ、2013年4月からは、61歳以上にならないと年金が一切支給されないということになりました。そのため、60歳定年後、年金も受給することができず、働いて賃金を得ることもできない、無年金・無収入層が生じてしまいます。これを防止するため、2012年の高年法改正によって、65歳までの継続雇用措置について、希望者全員の雇用確保義務が定められました。 |
|
高年法は、2004年の改正で、企業に、65歳までの雇用確保措置の実施を義務づけました。
2012年改正により、この雇用確保措置のひとつであり、多くの企業が採用している「継続雇用制度の導入」について、改正前の高年法で認められていた「労使協定による選定制度」が廃止されました(9条)。
そのため、2013年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければならないこととなりました。これを新聞報道などでは「希望者全員の継続雇用義務化」と呼んでいます。
改正高年法のポイントは、この①労使協定による選定制度の廃止のほか、②グループ企業における継続雇用拡大、③義務違反企業の企業名公表です。
以下、説明します。 |
|
2.1 労使協定による選定制度(継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み)の廃止
|
企業は、原則として、「希望者全員を継続雇用制度の対象者とすること」が義務づけられました。
しかし、これは、「希望者全員を65歳まで継続雇用すること」の義務付けではありません。継続雇用制度の対象とした上で、労働条件を協議して折り合わなければ、雇用しないことも原則として可能です(厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A」(厚労省HP http:/www.mhlw.go.jp)Q1-3・A1-3、Q1-9・A1-9)。
この例外は、以下の二つです。
|
(1)「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」(平24厚労告560号)
厚労省の上記「指針」により、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことができるとされています。就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできます。また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使協定を締結することができます。
ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意が必要です。 |
|
(2)経過措置
経過措置により、2013年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合、2025年(平成37年)3月31日までの間、選定基準を厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢以上の者を対象に利用することができます。
つまり、選定基準を、2016年3月31日までは61歳以上の人に対して、2019年3月31日までは62歳以上の人に対して、2022年3月31日までは63歳以上の人に対して、2025年3月31日までは64歳以上の人に対して、それぞれ適用できます。
しかし、これは、あくまでも、2013年3月31日までに労使協定で選定基準を定めている場合に限ります。現時点で労使協定を定めても経過措置の適用はありません。
|
|
|
|
2.2 グループ企業における継続雇用拡大
|
継続雇用制度は、グループ企業への受入れも含みます。グループ企業は、従来親子会社とされていましたが、改正により、関連会社を加えました(9条2項)。 |
|
|
2.3 義務違反企業に対する公表規定の導入
|
改正高年法第10条第3項は、義務違反企業に対する公表規定を定めました。厚生労働大臣は、高年法違反をした企業に対し勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができます。 |
|
| 3. 再雇用制度で、期間雇用(有期労働契約)とする場合の注意 |
|
多くの企業が、再雇用制度をとり、また、再雇用する場合の契約として1年間の有期労働契約としていると思われます。その場合の注意点を列挙しておきます。 |
|
3.1 「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針
|
「継続雇用制度を導入する場合において、契約期間を定めるときには、高年齢者雇用確保措置が65歳までの雇用の確保を義務付ける制度であることに鑑み、65歳前に契約期間が終了する契約とする場合には、65歳までは契約更新ができる旨を周知すること。また、むやみに短い契約期間とすることがないように努めること」と定めています。 |
|
|
3.2 有期労働契約の無期転換の問題(労働契約法改正18条)
|
改正労働契約法(2013年4月1日施行)により、再雇用後、有期労働契約の更新が繰り返され、その契約期間の通算が5年を超えると、労働者に、無期労働契約への転換権が発生します。そのため、企業としては、労務管理をきちんと行い、もし、転換権の発生を望まない場合、通算期間が5年を超えることのないよう留意が必要です。 |
|
|
3.3 労働契約法改正19条の雇止めの問題
|
改正労働契約法により、有期労働契約の更新が繰り返され、次の更新への期待が生まれると、更新拒絶ができないという判例法理が成文化されました。
企業としては、更新がされないことがある旨の就業規則、各雇用契約書への明記をすべきでしょう。自動更新条項は避けた方が良いと思われます。
経過措置に基づく労使協定による選定基準の適用の場面(定年後、再雇用するかどうかの場面)と、継続雇用の更新基準の適用の場面(例えば、定年後1年の有期労働契約として再雇用となった後、1年後に更新するかどうかの場面)は違います。前者は、高年法の適用の問題であり、後者は、労働契約法19条の雇止め法理に反するかどうかの問題ですので、混同しないようにしてください。
なお、私見ですが、労使協定による選定基準が適用されるとき(年金支給が開始される年齢のとき)の前後で、更新基準を異ならせることは、高年法の趣旨を没却するような基準でなければ、可能と考えます。 |
|
| 3.4 有期労働契約における不合理な労働条件の禁止(労働契約法改正20条)
|
改正労働契約法20条は、有期労働契約における不合理な労働条件を禁止します。
しかし、定年前の他の無期契約労働契約者の労働条件と相違することについては、特段の事情のない限り不合理とはされません(厚労省労働基準局長平成24年基発0810第2号)。
但し、労働市場の現況や定年退職後の雇用状況に鑑みて明らかに低額に過ぎるなどの特段の事情があるときは不法行為に基づく損害賠償請求が成立する可能性があります(Y運輸会社事件大阪高判H22.9.14参照)。 |
|
|
継続雇用制度をとった場合、労働条件をどのように定めるかは、各企業の悩みです。
改正高年法により、継続雇用者は増加します。そのため、総額人件費の上昇は避けられず、賃金・人事処遇制度全体を見直すことが必要ですが、制度設計は、各社ごとの実情に合わせて工夫するしかありません。
例えば、定年前と同じ職務内容と責任で引き続き働いてもらう人以外については、①再雇用後の賃金は、能力・仕事・成果に基づく賃金とする②短時間勤務、隔日勤務(勤務日・勤務時間を正社員とは異なるように限定・短縮)とする③時間外労働は原則としてさせない等のことが考えられます。また、企業によっては「退職金のピークを50歳台にする」「55歳でその後のコース選択(出世コース、リタイアコース)をさせる」等、独自の工夫をこらしているところもあります。
再雇用者に対しては、「第一線で働く」という意識から「若手のフォローや育成に回る」という意識の転換を行ってもらい、高年齢者でポスト・業務の独占をせず、若年者・新卒者に、過度のしわ寄せがいかないようにすべきでしょう。組織も新陳代謝を行っていくべきであり、賃金カーブの見直しは行うとしても、可能な限り新規採用数に影響を及ぼさないような設計が望ましいといえます。 |
|