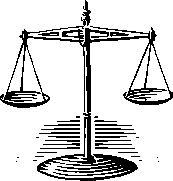
| �w ���s���Ј� �x �ւ̑Ή��� | 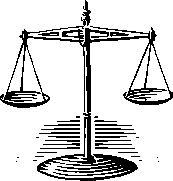 |
| �ٌ�m�@�ځ@�@���@�j�@�@�@ | |
�@��Ђɂ́A���s����g���u�����N�����Ј������邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B �@�x���E���̏�K�ҁA���̎Ј��Ƃ̋������ɖR�����g����ȎҁA�Z�N�n���E�p���n�����s���ҁA�d���̔\�͂��������Ⴂ�ҁi�u���[�p�t�H�[�}�[�v�ƌĂт܂��j�A�ٓ��E�]�������I���R�Ȃ����ۂ���҂ȂǁA�l�X�ȃ^�C�v�́u���s���Ј��v�����܂��B �@���x�o�ϐ�������E�o�u������ȂǁA�o�ς��E���オ��̂Ƃ��ɂ́A���̂悤�ȎЈ����Г��ɐ��������Ƃ��Ă��A��Ђɑ̗͂�����̂ŁA��������ł������Ƃ��ł��܂����B �@�������A���݂̂悤�Ȍ������o�Ϗ�̂��Ƃł́A���̂悤�ȎЈ�����u���Ă����킯�ɂ������܂���B �@�ǂ������炢���ł��傤���B �@���̖��ւ̑Ή���́A�{���́A���s���Ј��̃^�C�v�ɂ���ėl�X�ł����A�����̊W��A�ȉ��A�ǂ̖��s���Ј��ɑ��Ă���{�I�ɋ��ʂ�����@�����������܂��B
2.1.�@�o�c�ҁE�Ǘ��E���g�̈ӎ����v�ƁA���s���Ј��ւ̉��P�̓w�� �@�ŏ��ɂ����ӂ��Ă����������Ƃ�����܂��B �@���s���Ј�����Ђ��������̂́A�o�c�҂�Ǘ��E���A���̂悤�Ȏ҂����������ɍ̗p�������Ƃ�A�܂��A���̌�̖��s����ٔF������A���Č��ʂӂ�𑱂��Ă������ƂȂǁA�o�c�ғ��ɂ��ӔC�����邱�Ƃ������Ƃ������Ƃł��B �@���������āA�����Ő�������̂́A���ՂȎ��i���فj�ł͌����Ă���܂���B �@�u�����̉�ЂɁA���̂悤�Ȃ��Ɓi���s����j������Ј������܂��B���ق������̂ł����A�ǂ�������ł��܂����B�v�Ƃ����k�ɗ�����������܂��B �@�������A�����k�҂ɑ��A�u���܂ŁA���̎Ј��̖��s���ɑ��A���ӁA�w���⋳������A�܂��A�^������n�������o������Ȃǂ��Ă��܂������B�v�Ǝ��₷��ƁA�u�������B���ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ͂��Ă��܂���B�v�Ƃ������ɂȂ�A�u�ł́A���ق𑈂��āA�ٔ�������A�w�M�Ђ́A���̂悤�ȍs������ЂƂ��ėe�F���Ă����̂ł͂Ȃ��ł����B�x�ƌ���ꂽ��ǂ����_���܂����B�v�Ƃ���������ƁA�ق��Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ����X�ɂ��Ă���܂��B �@���s���Ј��ɑ��A��ЂƂ��Ďw���E����Ȃlj��P�̓w�͂����邱�ƂȂ��A�����Ȃ���ق��Ă��A�Ј�����@�I�ɑ���ꂽ��A�ٔ������A���قɂ͍����I�ȗ��R���Ȃ��i�u���ٌ��̗��p�v�j�Ƃ��āA���ق͖����Ɣ��f����댯������܂��B �@���s���Ј��ɑ��ẮA��ЂƂ��ĉ��P�̓w�͂�������ŁA����ł��Ȃ������߂Ă���킴��Ȃ��Ƃ��ɁA�ސE��������ق̓r��I������ׂ��ł��B �@���s���Ј��̑���l����ɂ������ẮA�܂��A��Ў��̂Ƃ��āA���s����ٔF���Ă��܂��Е����Ȃ��������A�Ǘ��E���u���傹��A���Ј��Ɏx�����鋋���͉�Ђ̂����ɉ߂��Ȃ��B�w�����Ă��A�����Ԃ��Ă��邩��A�X�g���X�Ȃ̂ŁA���Č��ʂӂ�����Ă������B�v�Ƃ����ӎ����Ȃ��������Ȃǂ�U��Ԃ��čl���Ă��������B �@�����A���̂悤�Ȃ��Ƃ��������̂Ȃ�A�o�c�Ҏ��g�̈ӎ���p����ς��A�Ǘ��E�̋���ے����[�������āA�Ǘ��E�Ƃ��Ă̎��o����������悤�ɂ��A���A��БS�̂ɁA���܂ŖٔF����Ă����悤�ȍs�ׂ͍��㋖����Ȃ����Ƃ����m������ȂǁA��Ў��̂̈ӎ������v����K�v������܂��B 2.2.�@��ԗǂ���́A�̗p���Ȃ����� 2.2.1�@�̗p�ɂ��� �@�����Ƃ��ǂ���́A���s�����N�����l�����̗p���Ȃ����Ƃł��B �@���ꂪ�A���s���Ј��ւ̑�Ƃ��āA��ԃR�X�g�i���ԁA�J�́A��p�j��������܂���B �@��Ђ��A���A�N���A�ǂ̂悤�ȏ����Ōق����́A�����Ƃ��Ď��R�ł��B �@��O�Ƃ��āA�j���ٗp�@��ϓ��@�A��Q�Ҍٗp���i�@�A�ٗp���@�A�J���g���@�̂S�̖@���ɂ��A���ʁE�N��E�J���g�������̈ӎv�̗L���Ȃǂɂ���č̗p��ɍ��ʂ�݂��邱�Ƃ͋֎~����܂����A���̂悤�ȍ̗p��ɂ��Ȃ���A�̗p�̉ۂ́A��Ђ����R�ɔ��f�ł��܂��B �@��������̗p���Ă��܂��ƁA���̎҂����Ղɉ��ق��邱�Ƃ͂ł��܂���B �@������R�l�ŏЉ�ꂽ�l�������Ղɍ̗p������A���͖�肪����A�Ɩ��ɑ�ώx�Ⴊ������Ƃ������Ƃ�����܂��B �@�̗p���f�ɂ������ẮA�Ⴆ�A�ȉ��̎������`�F�b�N���邱�Ƃ��l�����܂��B �@�@��Ђ����߂�\�͂�����Ă��邩�̋q�ϓI�Ȋm�F�i���Ў����̐��сA���ƍZ�̐��яؖ����A�e�펑�i�ȂǁB�ʐڂł̐l������̗ǂ���A�ِ�̍I�݂��ȂǁA�ꎞ�̈�ۂŌ��߂�̂͊댯�ł��j�B �@�A�����ɖ��s�����������킹����e���Ȃ����̊m�F�i�Z���Ԃ̊ԂɏA�E�ƑސE���J��Ԃ��Ă��Ȃ����ȂǁB�]�O�̋Ζ���ɑ���ސE���R�̊m�F���ł�����x�^�[�ł����A�u�v���C�o�V�[�̐N�Q�v�ƌ����Ȃ��悤���ӂ��K�v�ł��j�B �@�B���N��Ԃ̊m�F�i���N�f�f��f���ʂ̂ق��A�����^���ʂ̕a���m�F�ȂǁB�Ȃ��A�����Ƃ��āA�Ɩ��̖ړI�̒B���ɕK�v�Ȕ͈͓��Ōl�������W���邱�Ƃ͓K�@�ł��j�B �@���s�����N�����l�����ǂ����Ƃ������Ƃ��A��x���x�̎����E�ʐڂŌ��ɂ߂邱�Ƃ͓���ʂ�����܂����A�ł��邾���A�̗p���Ɍ��ɂ߂�ׂ��ł��B �@�M�Ђ̗̍p����A�q�ϐ��ɖR�����i�u���邭�͂��͂��Ƃ��Ă��邩�v�u������Ęb�����v���x�̊�Ȃǁj�A�ʐڊ��̎�ς�ٗʂɍ��E����镔�����傫���悤�ȏꍇ�́A�̗p������������Ƃ������߂��܂��B 2.2.2�@����E���X�� �@��������u����v���o���ƁA�������ɂ́A�����Ɍ������������ۂ���܂��B �@���Ȃ킿�A����ɂ��ƁA�u����v�́A�ٗp�_�������A����Ɏg�p�҂̉�����ۂ��ꂽ���̂Ɖ�����Ă��܂��B �@�������A�g�p�҂����̉���s�g���ē����������邱�Ƃɑ��ẮA�ٔ����͌������ԓx���Ƃ��Ă���A�������قɏ����������i�������̕K�v���A����̉��w�́A�l�I�̑Ó����A����҂ւ̐����j���K�v�Ƃ���Ă��܂��B �@�ŋ߂́A���̂悤�Ȃ��Ƃ����܂��A�u���X��v�Ƃ����A�u����v��������ɑO�i�K�ɂ���������Ƃ��Ƃ�����܂��B �@�u���X��v�ł͌ٗp�_��̐����Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ���Ă���A�����Ƃ��Ď���͉\�Ȃ̂ŁA�̗p���̌��ɂ߂�����Ƃ��́A�T�d�������āA�u���X��v�ɂƂǂ߁A����ɂ��̐l���̌��ɂ߂̂��߂̕������邱�Ƃ��l�����܂��B �@�������A��Ђ��A���X��҂ɑ��A�ق��̉�Ђ̓������X���f�点�Ă����悤�ȂƂ��́A���X��̎���ɂ��A�Ԏӗ��̎x���`������������ꍇ������̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B 2.3.�@�̗p���Ă��܂�����H 2.3.1�@���p���Ԓ��̉��� �@��ʂ̉�Ђ̏A�ƋK���ł́A�R�������x�̎��p���Ԃ�����A���̎��p���Ԍo�ߎ��ɁA���Ј��Ƃ��č̗p���邩�ǂ��������f�������̂Ƃ��āA�A�ƋK���Ɂu���p���Ԓ��A�Ј��Ƃ��ĕs�K�i�ƔF�߂��Ƃ��͉��ق���v���̒�߂�����܂��B �@���̂悤�Ȓ�߂́A����Ɠ��l�A�J���_��͐������Ă�����̂̊�Ƃɉ�����ۂ��ꂽ���̂Ɖ�����Ă���A�K�@�ł��B �@�̗p�����̒����̌��ʂ�A���p���̋Ζ����сE�ԓx�̕s�ǂȂǂɂ��A�̗p���ɂ͒m�邱�Ƃ̂ł��Ȃ�����������������A����A���̎҂��ٗp���Ă������Ƃ��K���łȂ��Ƌq�ϓI�ɔ��f�ł���Ƃ��́A���p���Ԓ��ɉ��ق��邱�Ƃ��ł��܂��B �@��ƂƂ��ẮA���̊��Ԃɂ����āA�ł��邾���A�Ј��̎��E�\�͂����ɂ߁A���ق��K�v�Ɣ��f�����Ƃ��́A���Ј��Ƃ���O�ɁA�K�i���������Ă��邱�Ƃ̋�̓I�����i�Ζ����сA�ԓx�̕s�ǂ��q�ϓI�ɏؖ��ł�����́j�������āA���ق��邱�ƂɂȂ�܂��B �@���p���Ԓ��̉��ق́A�{�̗p��̉��قɔ�ׂ�ƁA�L���͈͂ʼn��ق̎��R���F�߂��܂�����A���Ј��̌��ɂ߂́A�ł��邾�����̊��Ԓ��ɍs���ׂ��ł��B 2.3.2�@�V�l����E���C�̓O�� �@�����̊�Ƃł́A���p���Ԓ��̏����i�̗p��P�`�Q�T�Ԓ��x�j�ɁA�V�l����⌤�C���s���܂��B �@���̐V�l����E���C�͓O�ꂷ��ׂ��ł��BOJT�i�I���E�U�E�W���u�g���[�j���O�j�Ə̂��āA���ۂ͂܂Ƃ��ȋ���E���C�������A�����Ȃ�d���������邱�ƂȂǂ́A�~�X��g���u���������댯������ق��A���s�����N�����\���̂���Ј���\�ߌ��ɂ߂�@����킵�܂��B �@�����āA�ʏ�̎҂��B���ł���ڕW����B���ł��Ȃ��悤�Ȕ\�͂̒Ⴂ�҂�A�������i�ƁA�Љ�l�Ƃ��ē��R�Ȓ��x�̃R�~���j�P�[�V�������Ƃ�Ȃ��҂ɂ��ẮA���p���Ԓ��̉��قɓ��ݐ邽�߁A���̋���E���C���Ԃ̐��т�ԓx�����q�ϓI�����Ƃ��Ď��W���Ă������Ƃ��l�����܂��B �@����⌤�C�ɗv����R�X�g�i�l���A���ԓ��j���A���̌�̗l�X�ȃg���u���̗\�h���ł���Ȃ�ΕK�v�Ȃ��̂ƍl����ׂ��ł��傤�B 2.4.�@���Ј��Ƃ��Ă��܂�����H 2.4.1�@����E�w�� �@���p���Ԃ��o�߂��A���Ј��Ƃ��č̗p���Ă��܂�����A���͂��̎҂����s���Ј��ł��邱�Ƃ����o������A�ǂ�������悢�ł��傤���B �@�����Ȃ�ƁA�����Ȃ���ق��邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�Ⴆ�A��ʂ̉�Ђ̏A�ƋK���ł́A�u�]�ƈ��̋Ζ����т��������s�ǂŁA����̌����݂��Ȃ��A���̐E���ɂ��]���ł��Ȃ����A�A�ƂɓK���Ȃ��ƔF�߂�ꂽ�Ƃ��ɂ͉��ق��邱�Ƃ��ł���B�v�Ȃǂ̒�߂�����̂ŁA�g�p�҂��A���̒�߂ɂ���āA���[�p�t�H�[�}�[�̏]�ƈ������ق������ƍl���邱�Ƃ�����܂��B �@�������A�ٔ����̍l���ł́A�u���ق͍Ō�̎�i�v�ƈʒu�Â����Ă��܂��B �@���ق̎��R�̌y�d�ɂ����܂����A��{�I�ɁA���ق́A�J���҂̐����̊�b��D�����̂ł�����A�P�ɋΖ����т��s�ǂł��邱�Ƃ��F�߂���i���̂��Ǝ��̂���Ђ��q�ϓI�����������ďؖ����Ȃ���Ȃ�܂���j�Ƃ��Ă��A��Ђ�����E�w����s�����A�܂��A���̕����ւ̔z�]�\������̓I�ɒT��A���킦�āA���������ɊY������Ȃ�A�܂��͉����Ȃnjy����������n�߂āA�X���̋@���^����ȂǁA���̎�i��s�����Ă��Ȃ����ق�����Ȃ�����Ȃ��ƁA���ق͖����Ƃ���Ă��܂��܂��i�u���ٌ����p�̖@���v�A�J���_��@�P�U���j�B �@�o�c�҂�Ǘ��E�ɂ́A���̂悤�Ȏ҂��A�̗p���⎎�p���Ԓ��Ɍ������Ȃ������ӔC������͂��ł���A���s���Ј�������I�ɐӂ߂邱�Ƃ͂ł��܂���B �@�܂��́A��ЂƂ��āA���s���Ј��ɑ��鋳��E�w�����s���A���P�����邱�Ƃ��s���Ă��������B 2.4.2�@�������A�y����������i�K��Œ������� �@����E�w�����s���Ă��Ȃ����P���݂��Ȃ��Ƃ��́A���s���Ј��̍s�ׂ��A�A�ƋK���ɒ�߂��钦�������̎��R�i���R�j�ɊY�����邩�ǂ������m�F���Ă��������B �@�Y������Ȃ�A���̍s�ׂ̌y�d�ɂ����܂����A梐ӁE�����i�n�������o�����ď��������߂�j�ȂǁA�����Ƃ��y����������n�߂�̂���ʓI�Ǝv���܂��B �@�Ȃ��A���R�̂��Ƃł����A�A�ƋK���ɒ�߂��钦�������̎��R�ɊY�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����͂ł��܂���B���k�҂̒��ɂ́A�����Ȃ�u�ނ́����i���s���������āj�������̂�����A������������̂����R���B�v�Ƃ��b������������̂ł����A���̉�Ђ̏A�ƋK�����m�F���Ă��A���̍s�ׂ��ǂ̒������R�ɂ�����̂��A���m�ɂ����Ȃ����Ƃ�����܂��B �@���s���Ј��ɑ��钦���������l����Ƃ��́A�K���A�ƋK�����m�F���Ă��������B 2.4.3�@�ސE���� �@梐ӁE�����̒������������Ă��Ȃ����s�������܂炸�A������A�o�Β�~�ȂǁA���������̒i�K�������ď������Ă��ʖڂł���Ƃ����Ƃ��ɂ́A���ق��l���邱�ƂɂȂ�܂��B �@�Ȃ��A���������̑������́A�s�ׂ̏d�含�ɂ����̂Ȃ̂ŁA�K�������y����������ЂƂ��i�K�܂Ȃ��ƂȂ�Ȃ��Ƃ����킯�ł͂���܂���B�Ⴆ�A�����̋��⍘�Ȃǂ��̈ӂɐG�����Z�N�n���s�ׂ̏ꍇ�ɂ́A�ꔭ�ʼn��ق����蓾��ł��傤�B �@�������A���ّ����ƍl����ꍇ�ł��A�ٔ������A��ʂɁA���ٌ��s�g�Ɍ��������f���Ƃ邱�ƂȂǂ��l������A���s���Ј��ɑ��A����I�ȑސE�����߂�i�ސE�����j�̂��ǂ��ł��傤�B �@�A���A�ސE�������A�Z���Ԃɉ��x���������ސE�𔗂�Ȃǂ���A�s�@�s�ׂƂȂ��āA��Ђ����Q�����ӔC�������Ƃ�����܂�����A���ӂ��Ă��������B 2.4.4�@���ʉ��فE�������� �@���s���Ј����A�ސE�����ɂ������Ȃ��Ƃ��ɂ́A�Ō�̎�i�Ƃ��āA���قɓ��ݐ邱�ƂɂȂ�܂����A�������قɔ�ׂ��Ƃ��ɂ́A���ʉ��ق̕����s���₷���ł��傤�B �@�������ق́A���ʉ��ق����傫�ȕs���v��J���҂ɗ^���܂�����A�P�ɕ��ʉ��ق𐳓������邾���ł͑��肸�A�u���قƂ��ĉ��ق���v���Ƃ𐳓������邾���̒��x�ɒB���Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ���Ă��邽�߁A��ЂƂ��ẮA����ꂽ�ꍇ�A�������̂��߂̏ؖ����A��苭�����߂��邩��ł��B �@�������A���ʉ��ق̕������Ƃ�Έ��Ղɉ��ق��ł���Ƃ����킯�ł͂���܂���B���ق̌��͂𑈂�ꂽ�ꍇ�A���ٌ��s�g�ɋq�ϓI�ɍ����I�ȗ��R������Ƃ���邽�߂ɂ́A�����Ɍ������������߂��܂��B �@�o�c�҂�Ǘ��E����݂�A�u�ނ͓��R���ق���đR��ׂ����B�v�Ǝv����悤�Ȏ҂ł������Ƃ��Ă��A����܂ł̎����m��Ȃ���O�҂ł���ٔ��������āA�q�ϓI�ȏ؋��������āA�[�������邱�Ƃ��ł��邩�ǂ������l���Ă��������B
�@�ȏ�A���s���Ј��ւ̑Ή���Ƃ��āA��{�I�Ȃ��Ƃ�������������܂����B �@���Q�l�ɂȂ�K���ł��B |